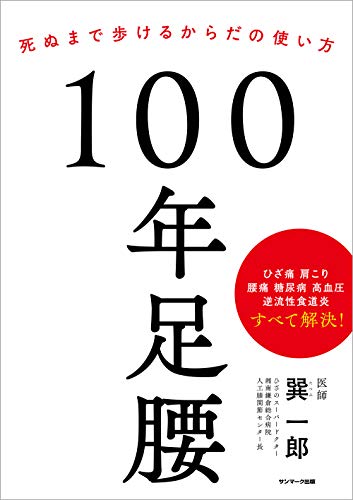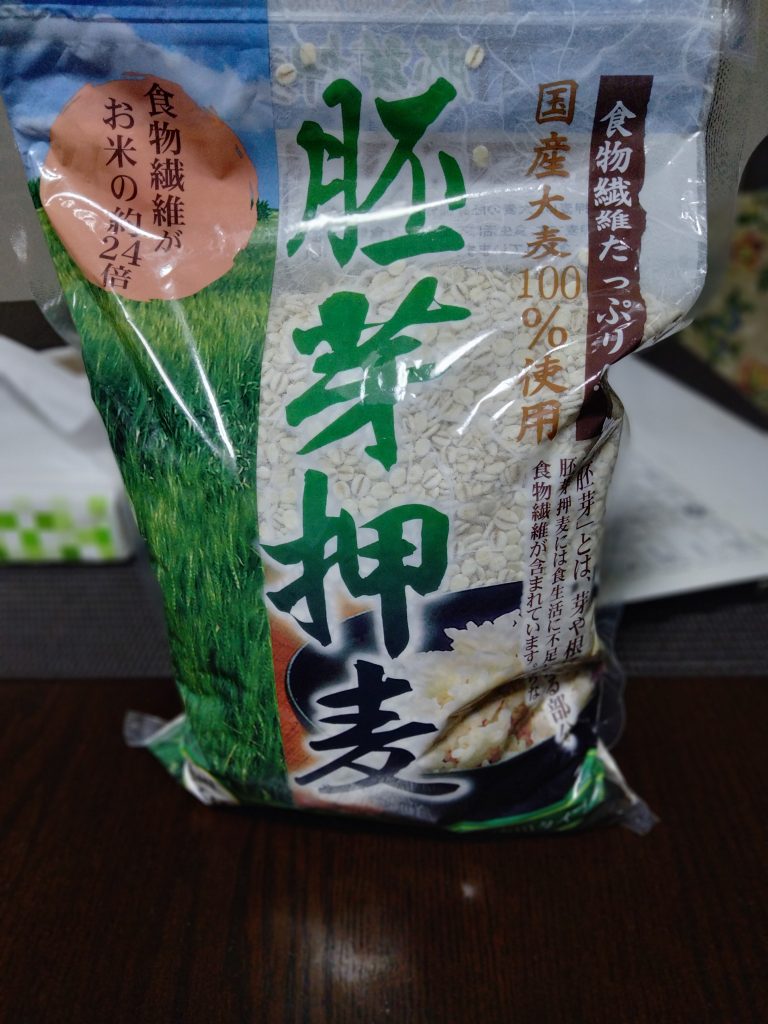【ブログ新規追加870回】

座りっぱなしは健康面でも非効率。積極的に立ち上がろう!
近年、「長時間座り続けると寿命が縮まる」という事実が広く知られてきていることをご存知?
アメリカの学会誌『American Journal of Preventive Medicine』は、「総死亡率の3.8%は座りすぎが原因となっている」ということを発表した。
寿命だけでなく生産性についても、座りすぎは悪影響を及ぼすようだ。
コーネル大学経済学部のアラン・ヘッジ教授は、「体のポジションを定期的に変えて、脳を休憩させることで、健康も生産性も向上する」と述べている。
で、せっかくなので具体的な「座る・立つ・歩く」のルーティーンを書き出してみた。
- 20分間座って仕事をする
- 8分間立って仕事をする
- 2分間仕事をやめて歩く
- 上記を繰り返す
定期的に立ち上がって動き回ることで、脳への血流が増し、頭の働きがよくなる。
アメリカでは、スタンディングデスクを取り入れる会社も増えているため、立って仕事をすることも現実的。
しかし日本では、上記のルーティーンを厳密に遂行することは難しいかもしれない。
その場合には、30分おきにウォーターサーバーに水をくみに行ったり、お手洗いに行ったりすることを心がけるのがおすすめ。
長時間座り続けることを意識的に回避し、集中力を高めて効率よく仕事や家事に勤しみたいものだ。
★
わたしの母が、生前、実弟の家で電子部品の製造をやっていた時のこと。
冬になると、トイレがとても近くなるから、どうしても「水分」を控えるようになったのだそう。
そして、水分を摂らないから、トイレの心配が少なくなったと、勝手に思い込んで午前中3時間も仕事に没頭していたそうだ。
もちろん、午後も1時から3時までぶっ通しで仕事。3時過ぎから5時までも仕事。
結果、座りっぱなしで立つこともほぼなく、トイレも3回行くぐらいで軽々とやっていたのだが、1ヵ月もそんなことを続けていたら、極度の脱水症状でひどい膀胱炎を発症してしまった。
やっぱり、適度な水分補給と、立つことの重要性をこの時、母も周りの仲間もひしひしと感じたそうだ。
わたしも、家で集中して仕事をしたりするときは、スマートウオッチでアラートが鳴る設定にしているんだ。
30分以上、座りっぱなしだと、スマートウオッチがブルブルと鳴りだし、立って歩き回ってください!とお話しし始めるから、お茶入れたり、それこそトイレに行ったりと。
立ったり座ったりが頻繁だと、何だか落ち着かないけれど、身体の巡廻を止めてしまわないためには、「立ったり座ったり」のメリハリが物凄く大事。
わたしの母みたいに膀胱炎を起こしちゃったら大変!
というわけで、「20分仕事→8分立って→2分歩いて」これを習慣にしてみよう!