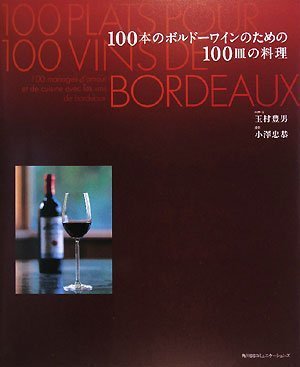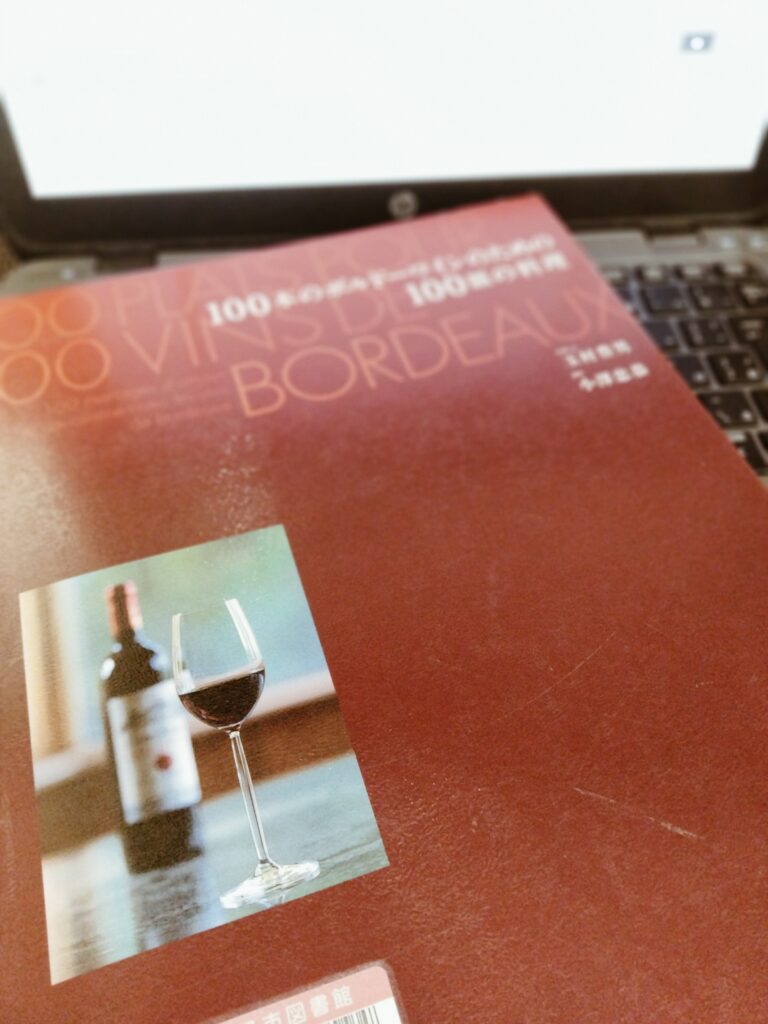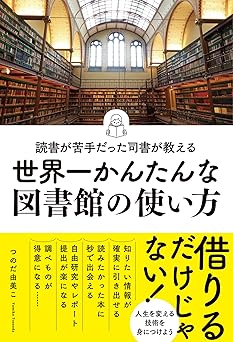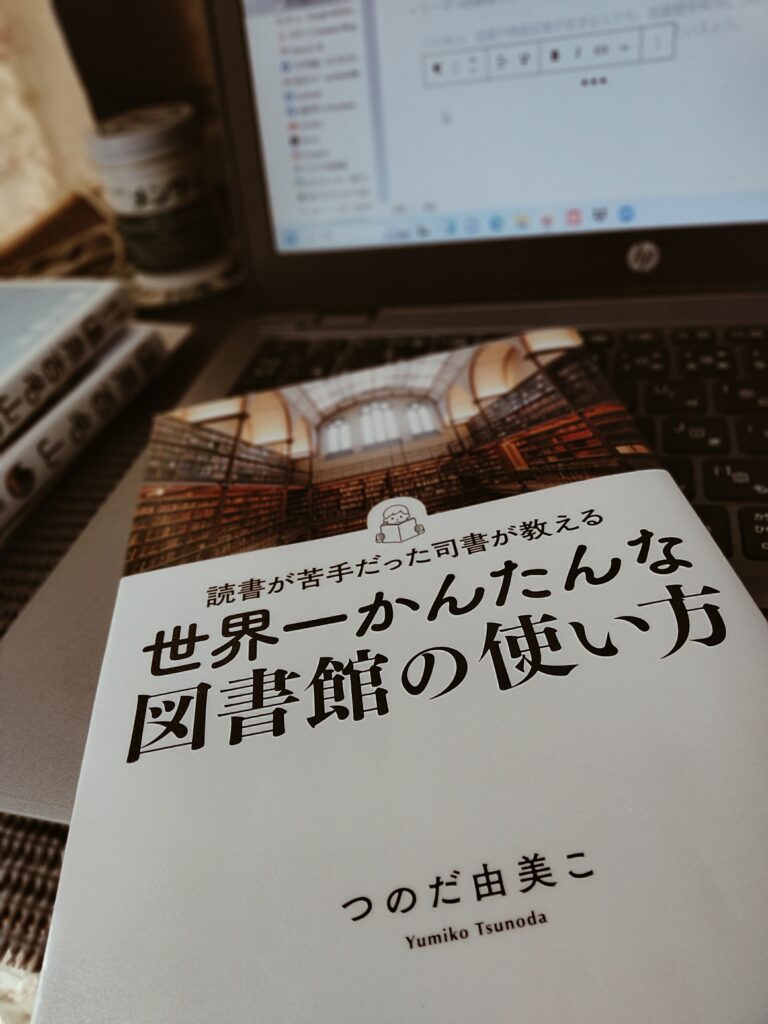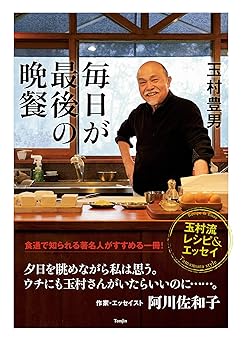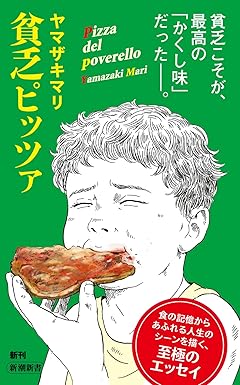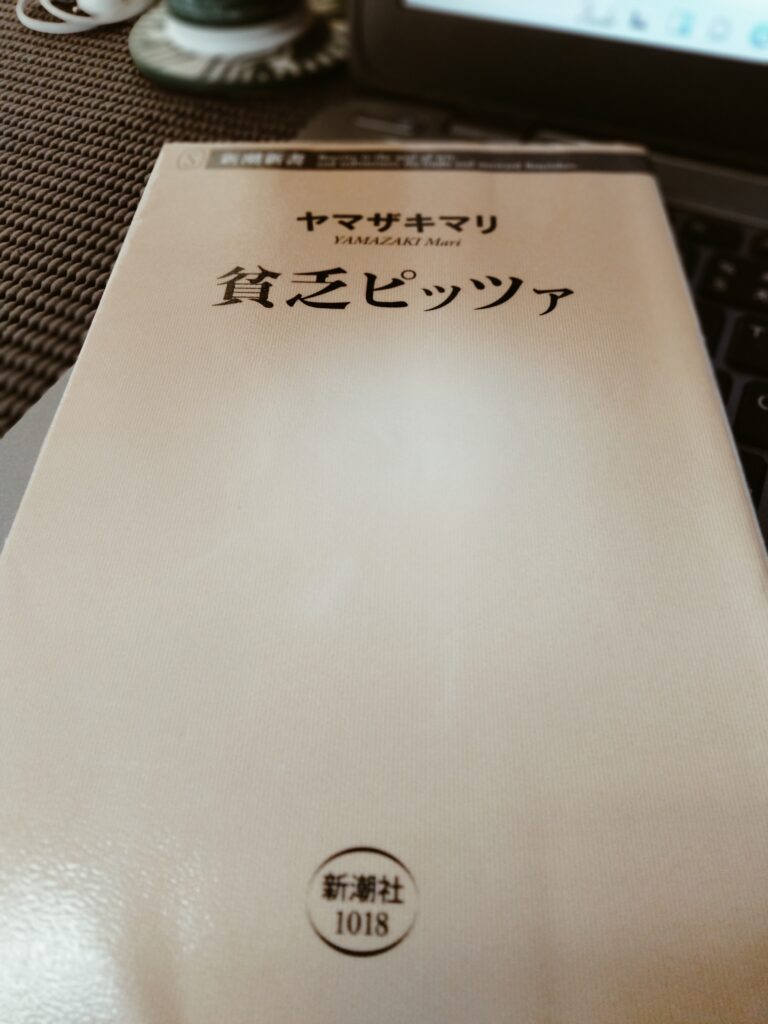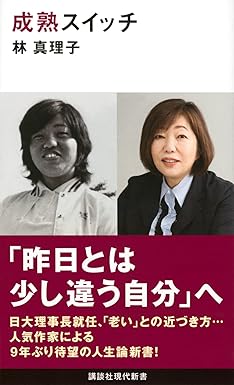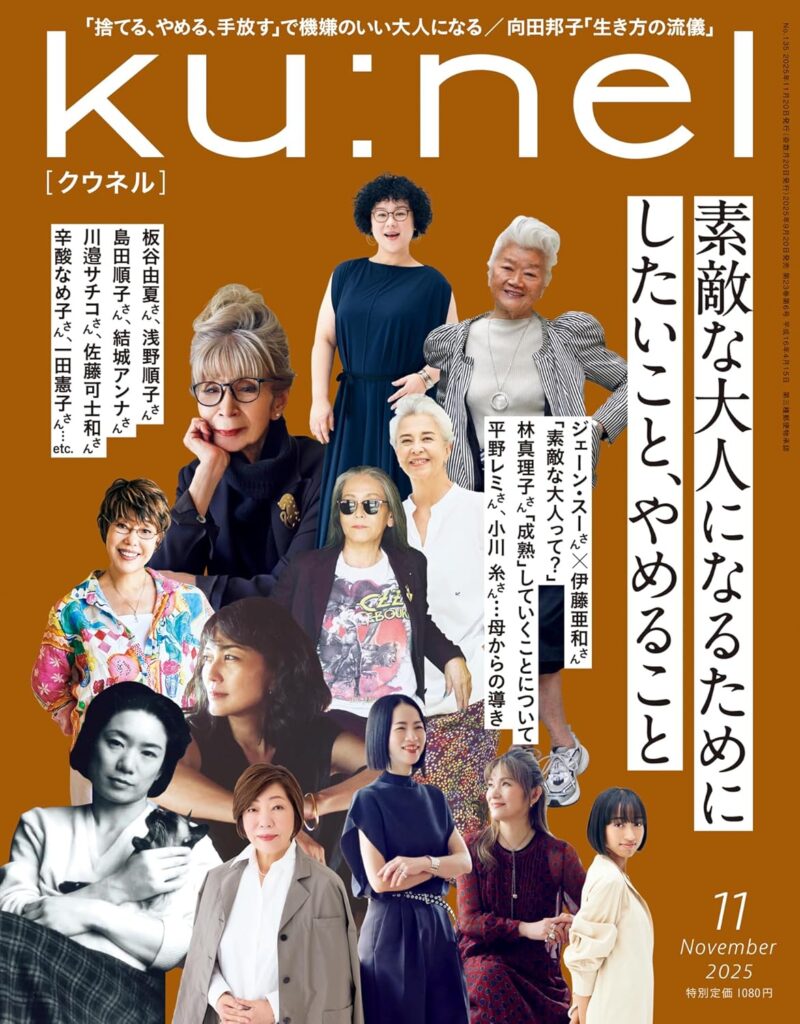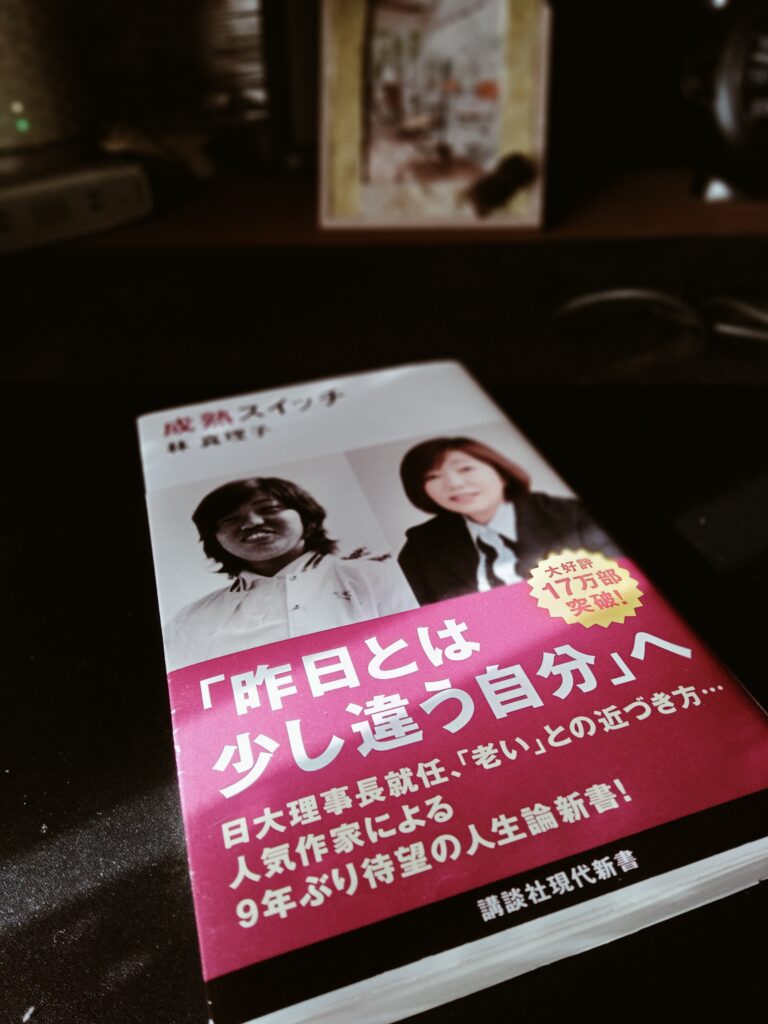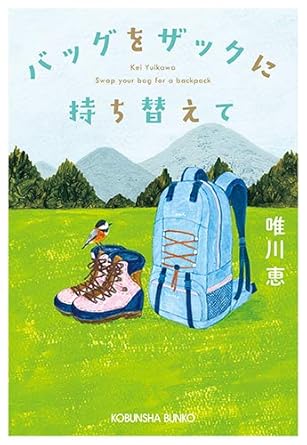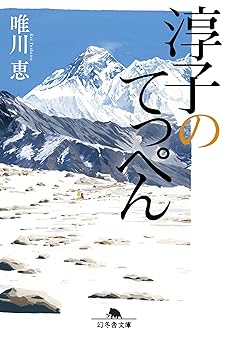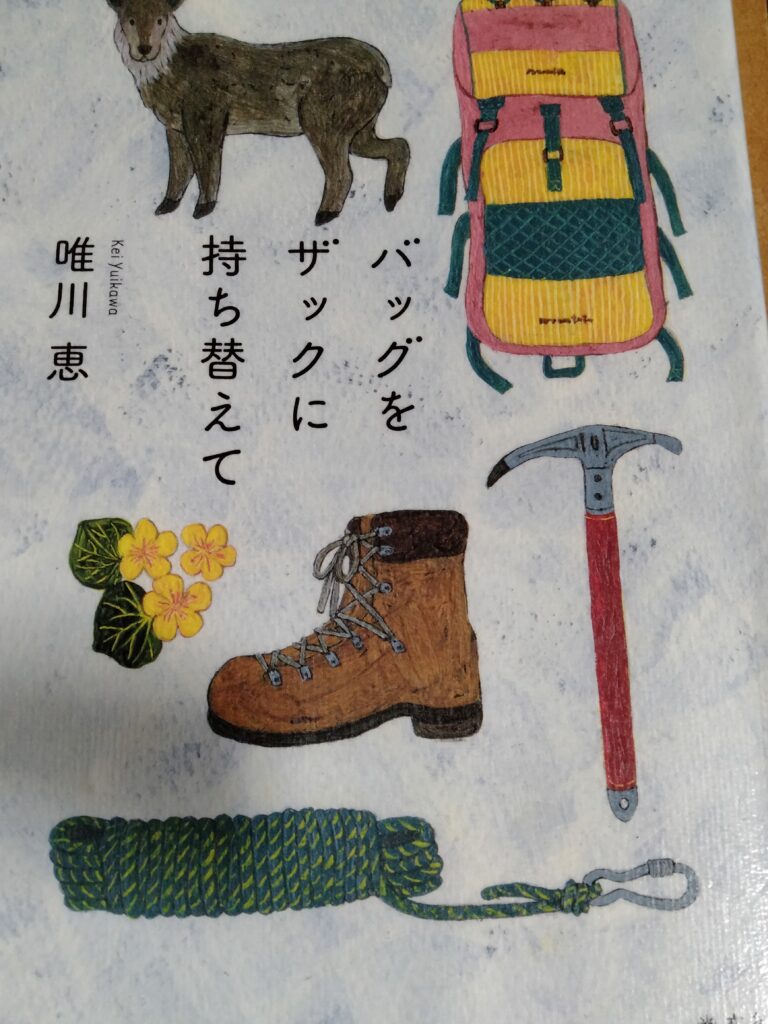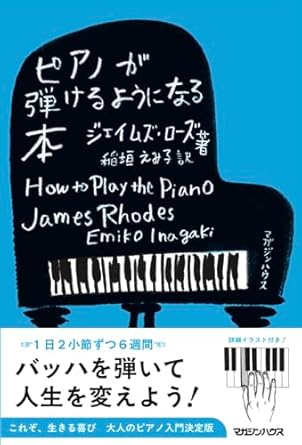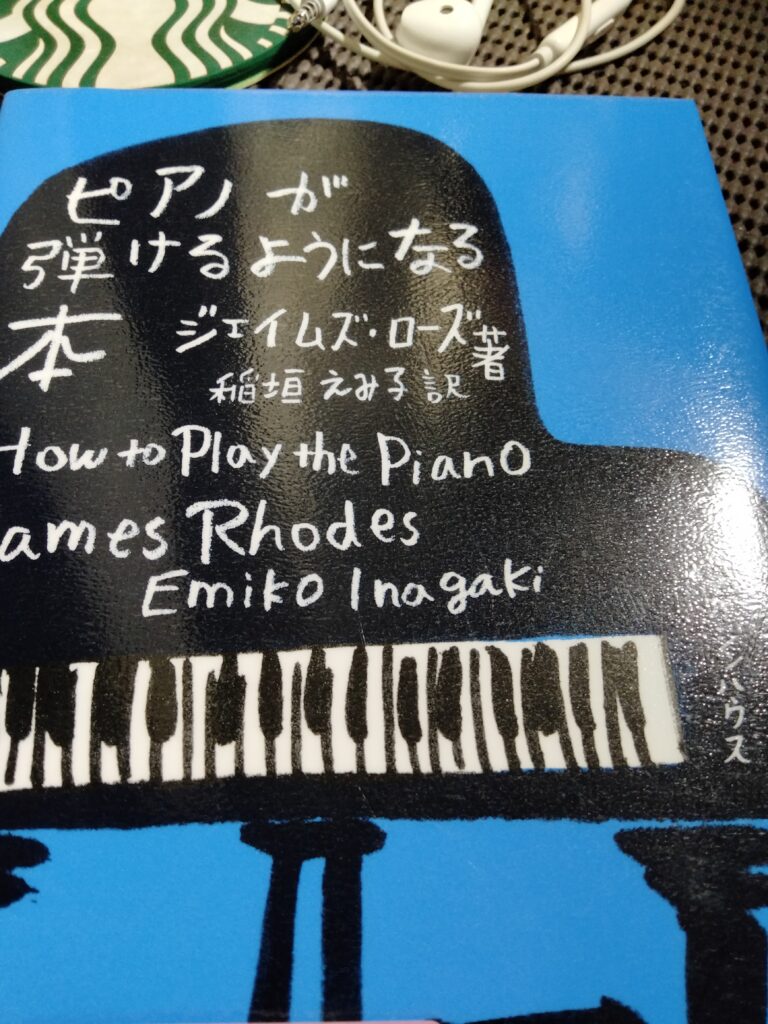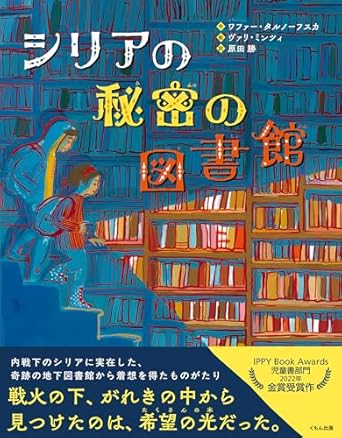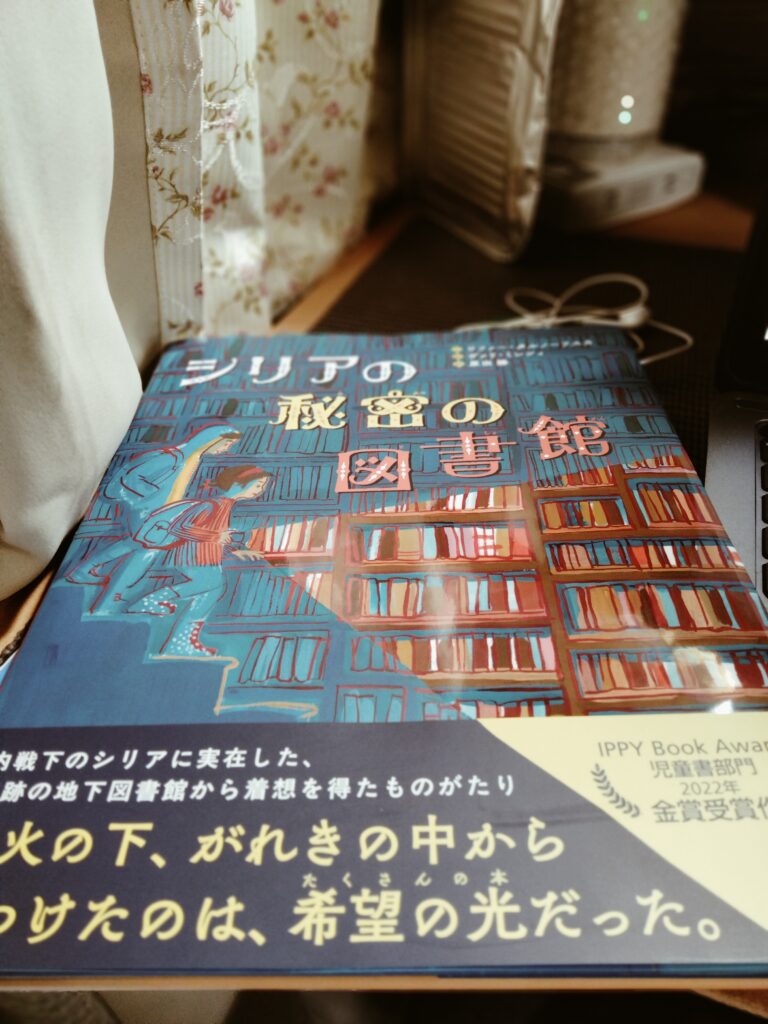【ブログ新規追加1443回】
『温泉博士が教える最高の温泉~本物の源泉かけ流し厳選300』小林 裕彦・著(集英社)

簡単レビュー
成分表示偽装や誇大広告は、もってのほか!
弁護士でもある温泉博士がうそ偽りのない「真の名湯」選びを伝授。
20年超にわたって全国の温泉を巡っている著者が「七大ドバドバ温泉」「十大絵になる温泉」「五大強烈臭温泉」「七大足元湧出温泉」など、
独自のジャンル別におすすめ温泉を紹介!
~本書の重要ポイント~
温泉旅館の公式サイトなどでは、かけ流しといっても塩素殺菌の有無は必ずしも明らかにされていない場合があります。いくら建物が立派で料理の美味しい温泉旅館に泊まったとしても、それが循環風呂だったりすると、本当の温泉に入ったことにはなりませんし、効能も家庭の風呂とさほど変わりません。
いい温泉とは?と聞かれたら、私は「足元湧出の温泉ですよ」と答えることにしています。というのは、足元湧出温泉は、人口掘削をしておらず、大事から自然に湧いていて、純度も鮮度も100%の温泉だからです。 成分の濃さと良さのため、本当に癒されますし、疲れます。源泉の成分が体に浸み込んで、本当に効いているなと実感できる温泉です。
最近は、泉質が優しくて、ツルツル感が高くて、ぬるめで長時間入れて、湯量の多い、本物の良質かつ新鮮なかけ流しの旅館によく宿泊します。(本文抜粋)
もくじ
第1章 温泉との邂逅
第2章 温泉業界の深くて暗い闇
第3章 良い温泉とは
第4章 ジャンル別おすすめ温泉
第5章 心を鬼にして選んだ地域別おすすめ温泉
<著者プロフィール>
小林裕彦(こばやし・やすひこ)
小林裕彦法律事務所 代表弁護士
1960年大阪市生まれ。84年一橋大学法学部卒業後、労働省(現厚生労働省)入省。89年司法試験合格、92年弁護士登録。2005年岡山弁護士会副会長。19年(平成31年度)岡山弁護士会会長。
11年から14年まで政府地方制度調査会委員(第30次、31次)。14年から岡山県自然環境保全審議会委員(温泉部会)。現在は岡山市北区弓之町に小林裕彦法律事務所(現在勤務弁護士は9人)を構える。
企業法務、訴訟関係業務、行政関係業務、事業承継、事業再生、M&A、経営法務リスクマネジメント、地方自治体包括外部監査業務などを主に取り扱う。
著書に『これで安心!! 中小企業のための経営法務リスクマネジメント』等。
★★★
温泉に行きたい!!!という心境になったら「疲れを癒す旅」を考えるのが普通よね。
ところが、本書の著者である小林裕彦氏によると、「本物の源泉かけ流し」に入浴すると、心も身体も癒されるどころじゃなくて、「身体の奥底から力が漲る!」のだそうだ。
わたしも、今年はじめて、草津温泉の「源泉かけ流し」に2度入浴したが、小林裕彦氏が言う「身体の奥底から力が漲る!体験」をした。
忘れられない温泉になった。
そして、今後は「源泉かけ流し」に入れる温泉宿を見つけて行きたい!と、願っているところなのだ。
そのぐらいの衝撃を草津温泉では受けたのだ。
湯治なのかな・・・。本当に身体の具合を良くするために温泉に入る。もう、そういうお年頃になったのかしら?(笑)
さ、年末進行も粛々と進めながら、「源泉かけ流しに入る」というご褒美をぶら下げて、仕事や家事を頑張ろうっと。
それでは、また!
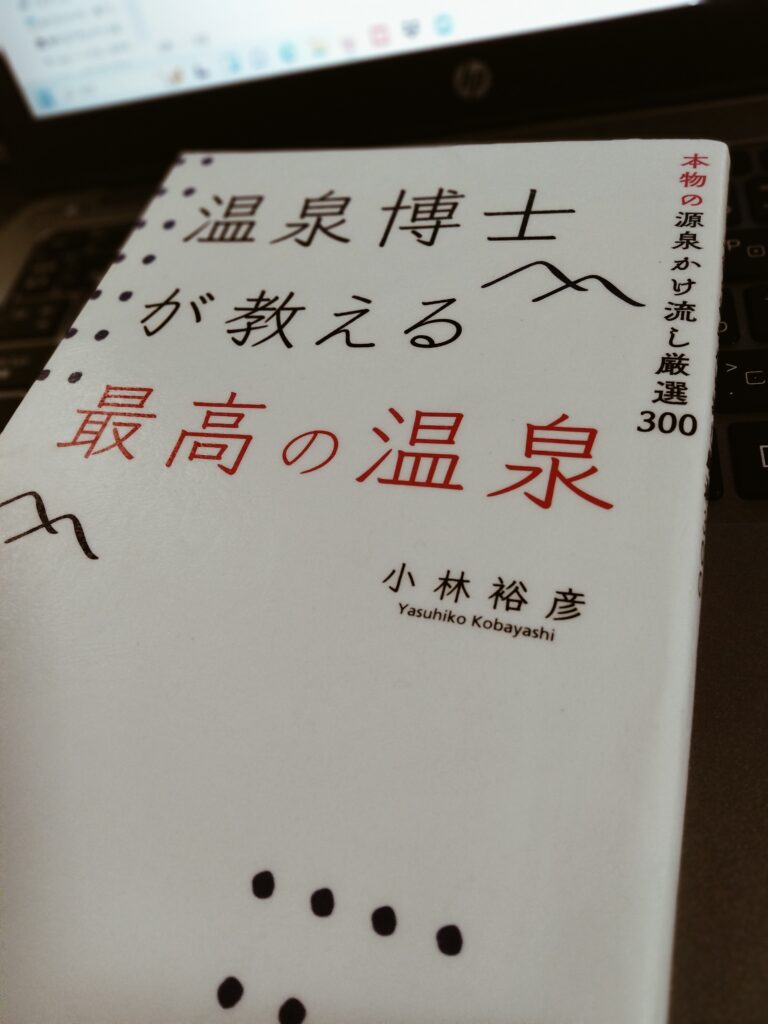
-------------------------------------------------旧記事更新