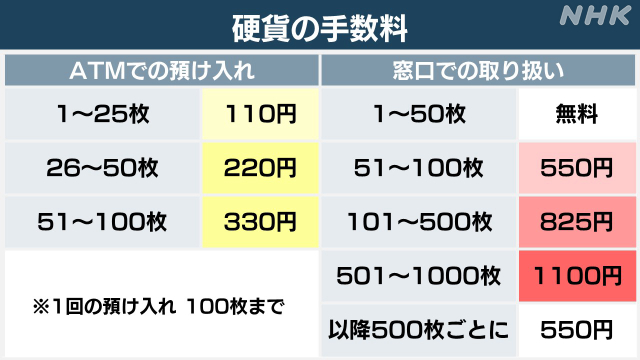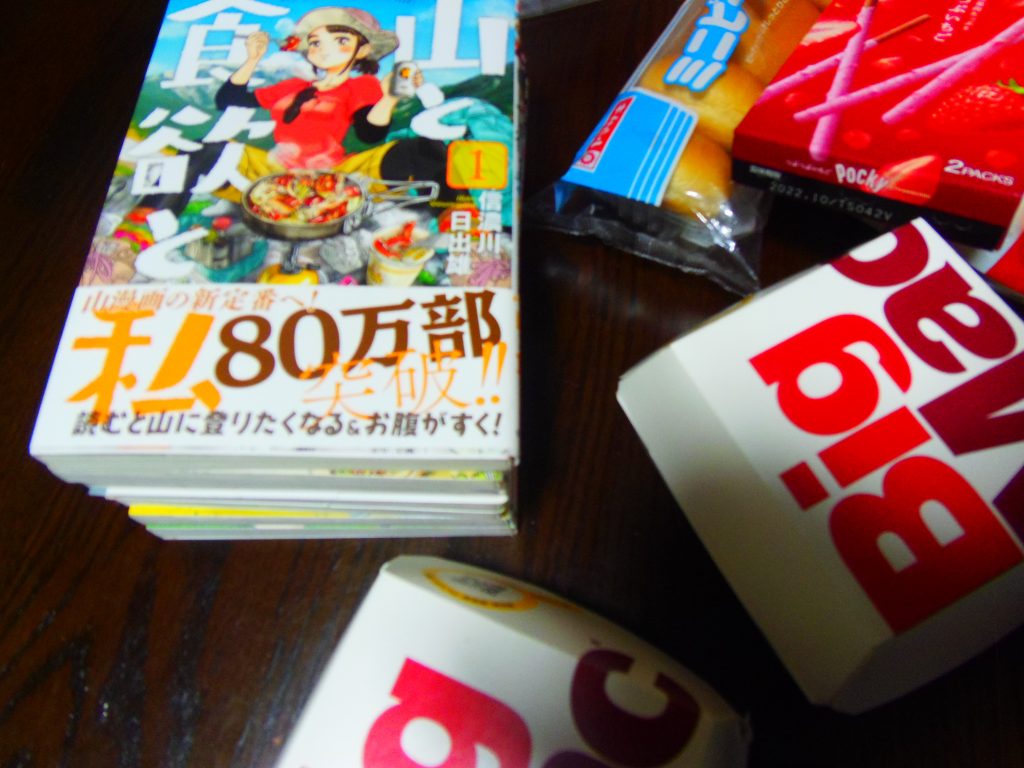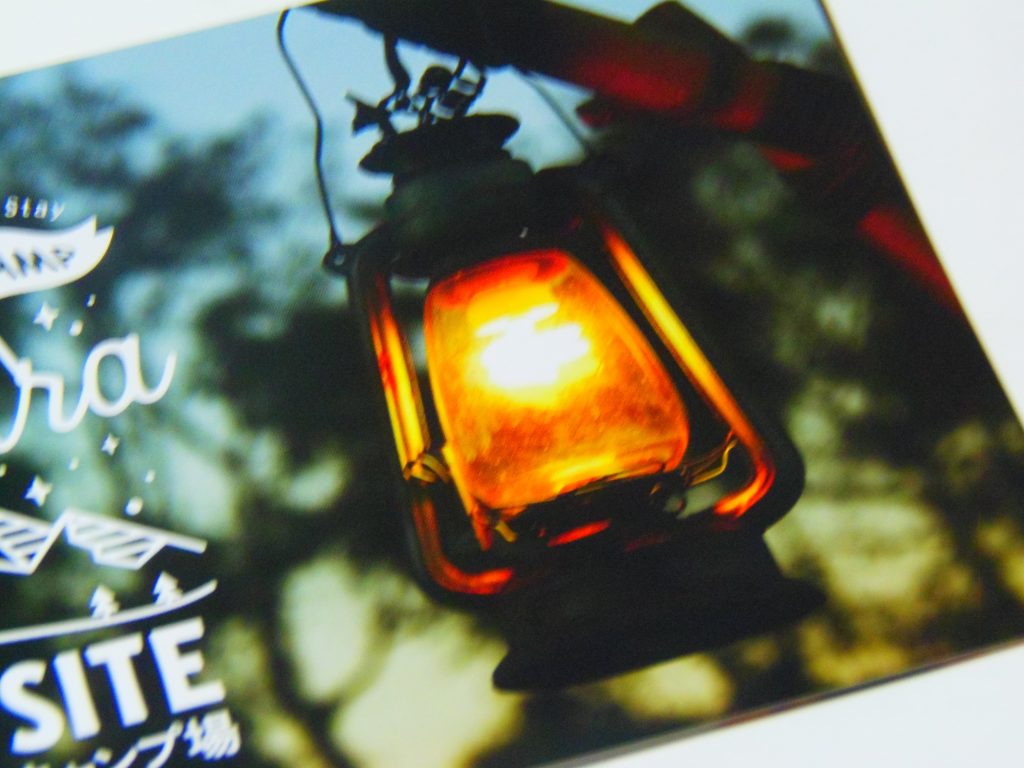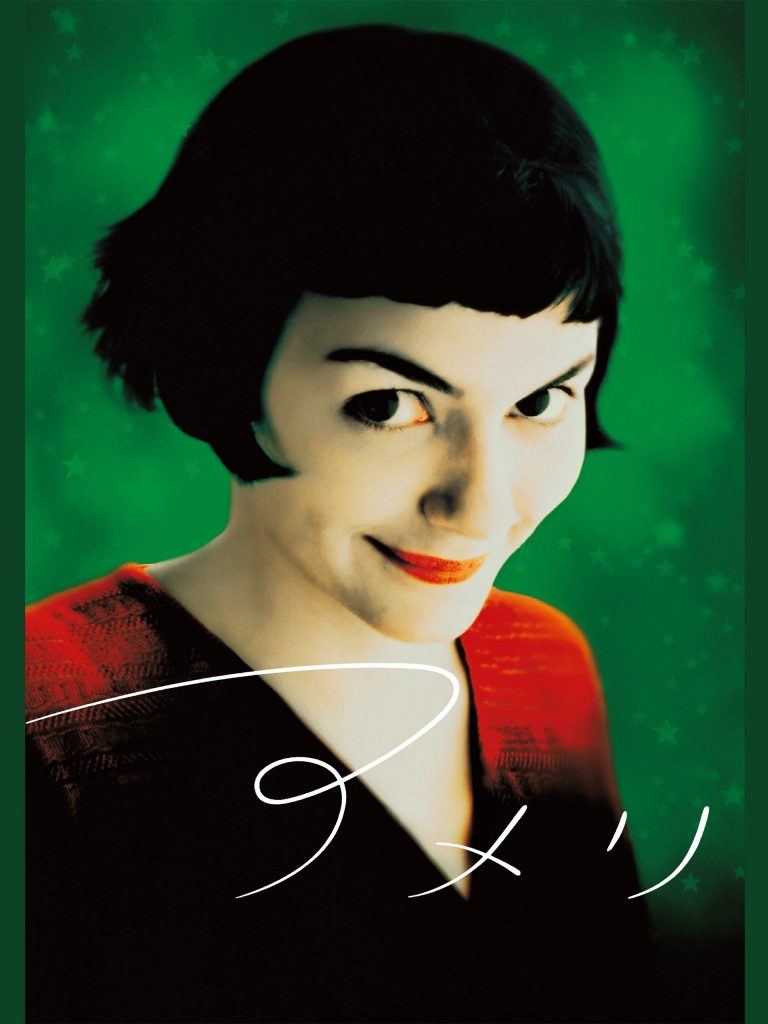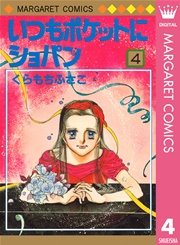【ブログ新規追加612回】

先日、吾妻山の頂上で公園の芝生を養生する地元のボランティアの方から、夫が「吾妻山で日本水仙の見られるポイント」をうかがった時のこと。
山の裏側にいくつも点在していると、下山途中でも水仙の園があるなど、養生の手を止めて教えて下さった。
※養生とは・・・衛生を守り健康の増進に心がけること。また、建築工事などで破損防止のための手当てを指す。(資料元;https://kotobank.jp/word/%E9%A4%8A%E7%94%9F-653073コトバンク)
下↓の写真が養生中のおじさんたち。すごくきれいな芝生だった。こうやって手入れされるこの公園はほんとにしあわせだね。

聞きたいことを的確にお話し下さったあと、「今日は暖かいから富士山見えないね」と。
おじさんいわく、「う~~~んと寒くならないとくっきりはっきりとした富士山が見えない」と、地元民ならではの情報を教えてくれたんだ。
ムダのない話ぶりがとてもすてき!いい出会いだった。
★
一方のマウント(自慢)おじさんとの出会いだが、昨年末にダイヤモンド富士を見に高尾山へ登った時のこと。
山頂で、一番よいと言われている場所に運よく場所取りをした。ちょうど、その場所から見える山々は20座ほど。素晴らしい眺めだった。
しばらく眺めを堪能していると、わたしと夫の間に突然、割り込んできたおじさん。
おじさんは、今は登山も写真も辞めちゃったんだと。聞いてもいないのに、話始めちゃった。
じゃあなんでここに?と聞けば、嬉しそうに「誰かと話がしたくてね・・・」と。
どうやら、ダイヤモンド富士の見られる期間は毎日登って来ているらしい。
な~んだ、登ってるじゃん!と、ツッコミたくなったよ(笑)
そして、そのまま、わたし達を相手に山登りの話を延々30分ほど述べ始めた。
「ここから見えるあの山は御正体山・・・」とか説明を入れながら登った当時の自慢話をする。(山小屋のオーナーは知り合いだとか、熊に遭遇したとか)
でも、目の前に山の表記があり山の名前と標高は教えてくれずともわかるのだけど。
おじさんが、なぜ、30分も話続けているのか?
それは、全部この20座を登った経験があるからだと。それも何度も登ったんだと。
だから、自分の話のストーリーを全部しゃべると30分かかるらしいの(驚き!)
途中で、わたしは気がついたのだけど。
「ああ~~、全部しゃべりたいんだな!」ってね。
こういうのを、マウンティングというのだな。迷惑しごくだわ。
しかし、まったく悪気はなさそうなおじさん。巷のネットにある「趣味マウンティング」のような見下しマウントではなかった。
そもそも、全部登った話なんてわたし達には関係ないよ。
最初は「すご~~い!ですね」とかある意味おじさんを称えつつ、棒読み状態での受け答えを30分続けたんだ(笑)
「早く、気づいて!」
「わたし達は山そのものの情報なら聞く耳を持つけど、20座を制覇したあなた個人の話は聞きたくない!」のだと言いたかった。
で、きっかり30分で「こりゃ!しつれいしました!」と言って立ち去っていった。
くさいけど、マウンテン(山)でマウント(自慢)された話(大笑)
★
これって、SNSでもおんなじかもしれないね。
わたしのSNS交流にも、それまで仲良くやりとりしていた人が、ある日を境にパタッといなくなる現象が時折あった。
きっと、こういう現象は先のマウントが原因じゃないかな~~~と、立ち止まり謙虚に考えて来た。
パタっといなくなったネット上の友人達は、「わたしからの有益な情報」なら受け取るけれど、「わたしのあーだ、こーだの仕事や趣味の話」はシャットアウトしたのだと考えた。
まるで「そんじょそこらのおばさんのブログを読む必要はない!」と、言われたような苦い気分。ちょっと被害妄想的かしら(笑)
わたしは、その人達に一切マウントした覚えはない。
ブログに書くのはあくまでも、わたしの経験したものごとだけに絞って書いている。誰かを揶揄するようなものはまったくといっていいほどない。
このブログの本意は「人生を最後まですがすがしく生きるためにやっているちょっとしたコツ」を文章にまとめているだけだ。
だから、誰でも思い立ったらすぐできることばかり。まあ、気にせずやってきてはいるけれど。
で、最後になったが、どっちのおじさんがいいか?と言えば、「聞いたことに的確に答えてくれるおじさん」で、迷惑なのは「聞いてもいないのに自分の話をしゃべりまくるおじさん」の話を書いてみた。
さて、わたしも「読みたくもない話」を書いてしまわないように、日々精進してまいります(^^♪