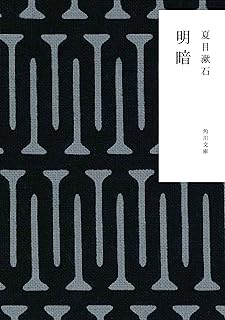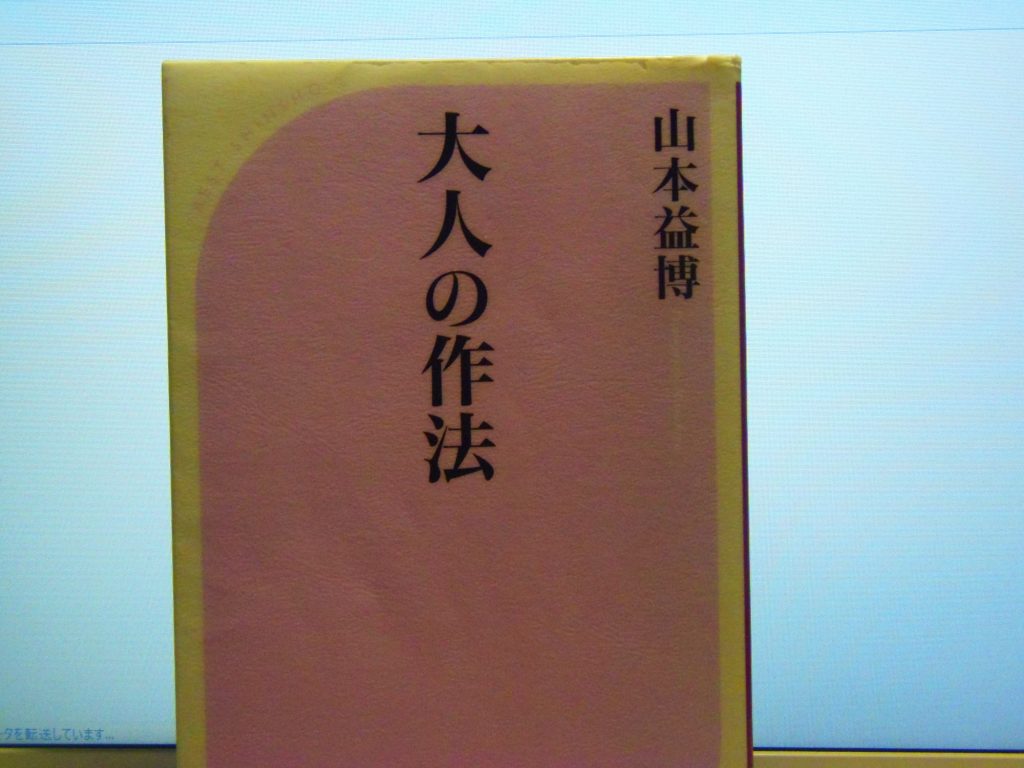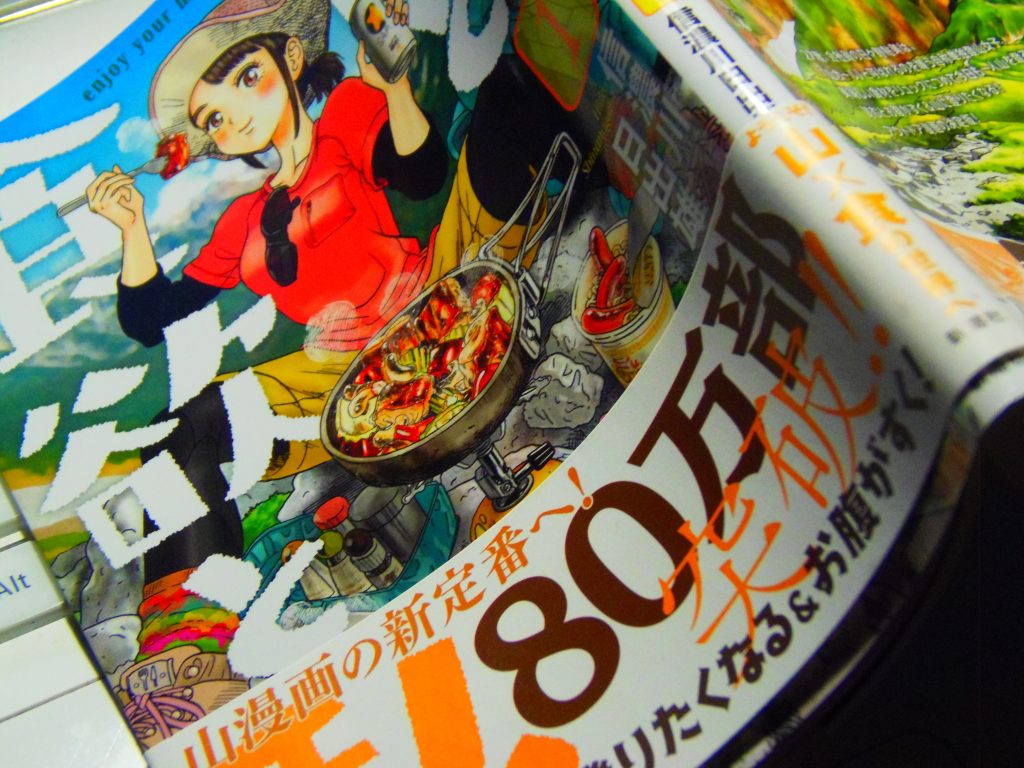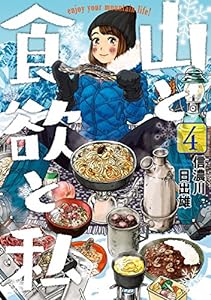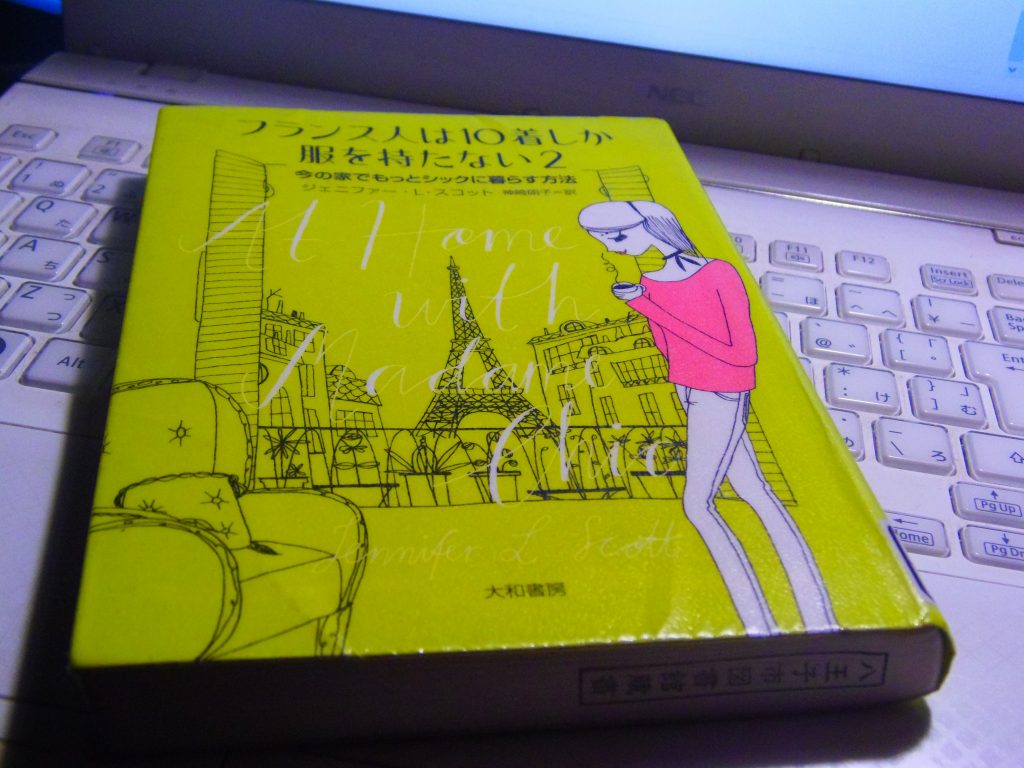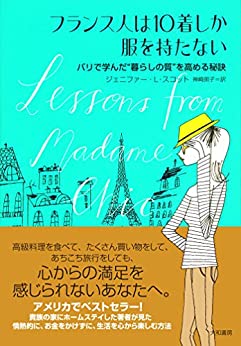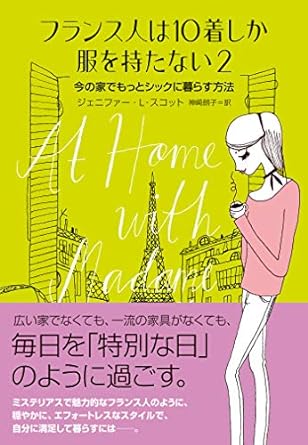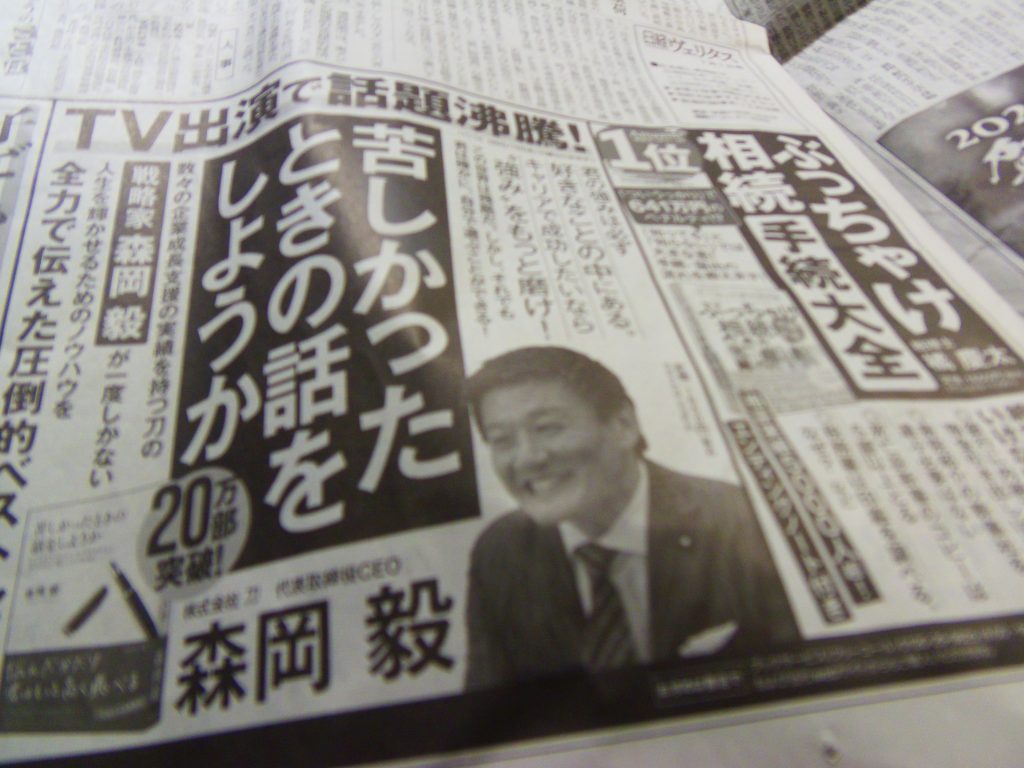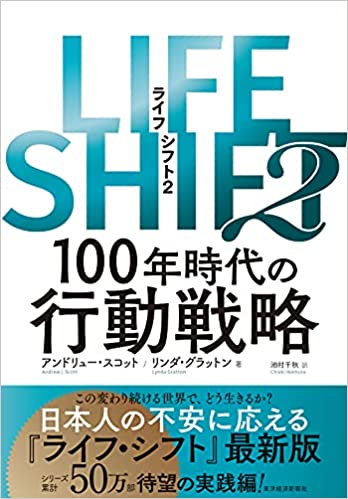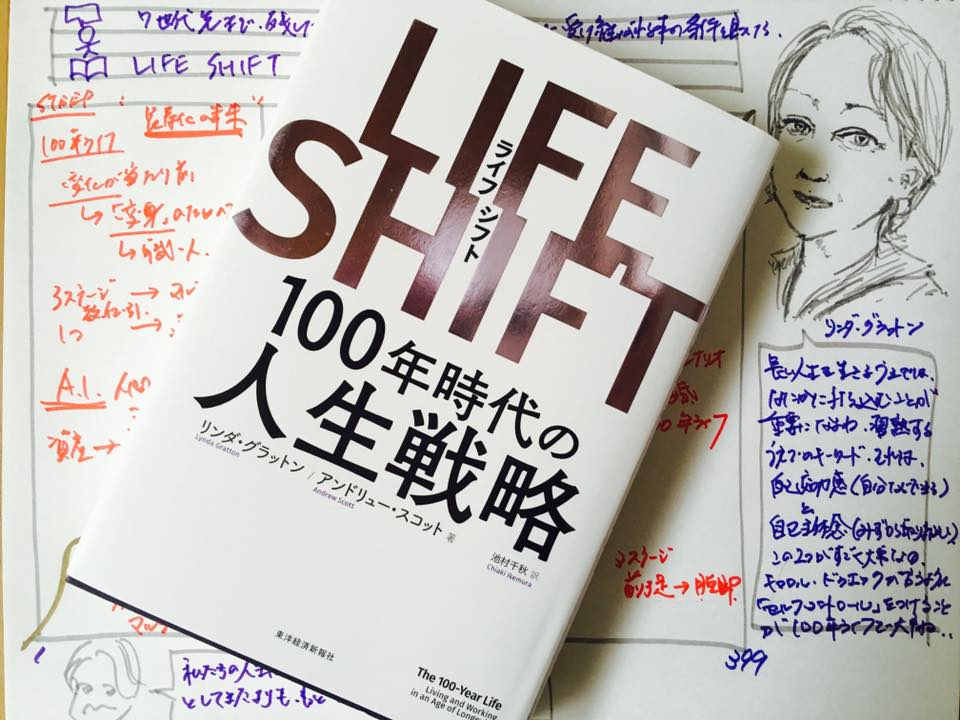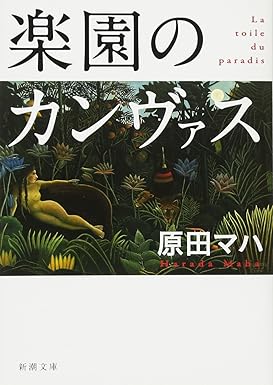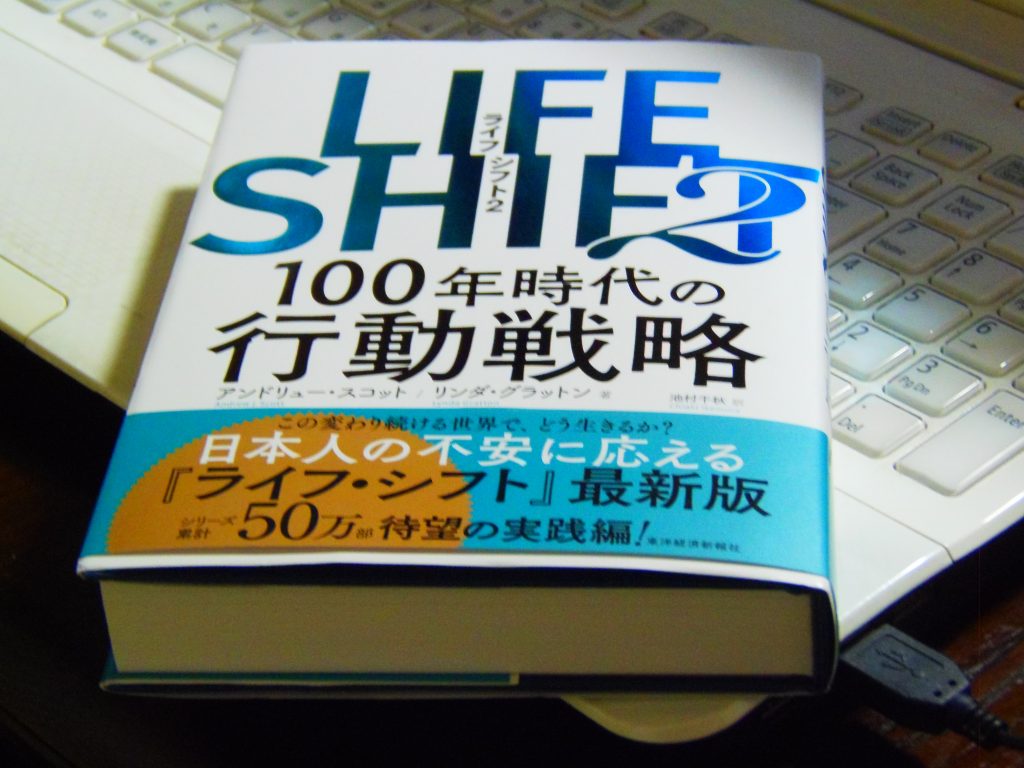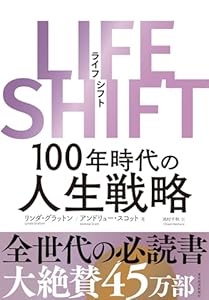【ブログ新規追加643回】
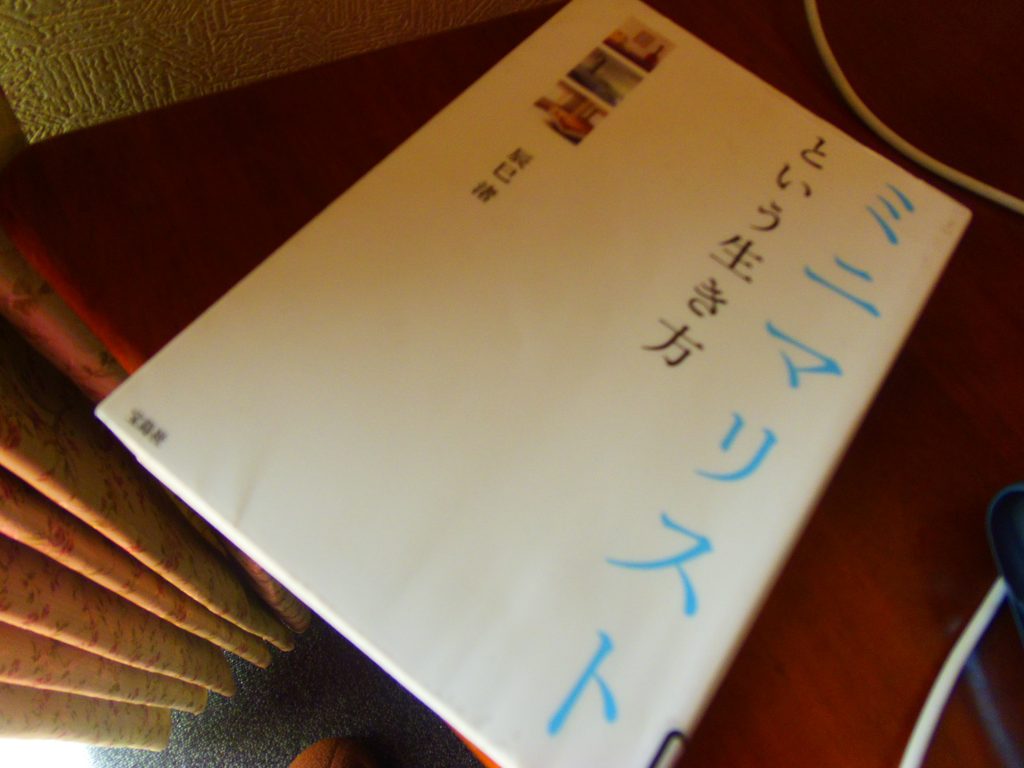
弥生・3月になった。
新年度を迎える準備に忙しくなる季節の到来だ。
身辺の整理をされる場合もあるだろう。
そんな時に人生を変えるような「振り切った片づけ」をしたい!と思っているなんて方にうってつけの一書を紹介する。
『ミニマリストという生き方』辰巳 渚・著
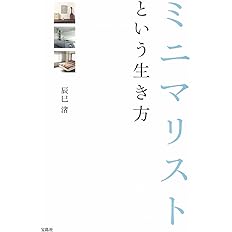
• 簡単レビュー
モノを最小限に減らして暮す「ミニマリスト」という考え方を持つ人たちが最近注目を浴びている。
しかし、ミニマリストが普通と違う考え方や普通の暮らしを避けているわけではない。
本書では、そんな最小限にモノを減らすに至った経過や原因、ミニマリストのゴール、これだけは手元におく、など等身大の5人のミニマリスト達への取材が読めるある意味片づけに悩む人へのサポートとなる一書だ。
本書に散りばめられたミニマルにスッキリと暮らすきっかけや考え方は、ひとり暮らし、夫婦ふたり暮らし、子どもと家族4人暮らしなど、形態別に書かれている。
著者・辰巳 渚さんも元ミニマリストだそうだ。ミニマリストになるきっかけ、プロセス、現在の暮らしぶりや考え方もレポートされた興味深い名書だ。
★
さて、「ミニマリスト」という言葉と考え方を生き方にまで昇華させたのはいったい、いつのことだったのだろう。ちょっと、調べてみた。
『ぼくたちに、もうモノは必要ない』で披露された、ミニマリストの定義は二つあって、① モノは自分に本当に必要な最小限にすること。② 大事なモノのためにそれ以外を減らすことを「ミニマリズム」とし、そうする人のことを「ミニマリスト」と呼ぶ。
自らを定義し、その定義によって自らの存在を宣言する・・・ということらしい。
だって、片づけブームはもうかれこれ20年ぐらい前から始まっていて、モノを減らすことにもすっかり慣れた世間があったハズよね。
それでも、何だろうな「ミニマリスト」は別の空気をまとっているみたいなもので、この呼び名自体に価値を見出した人も多そうだ。
今回取りあげた『ミニマリストという生き方』の中で印象的だったのが、お笑い芸人の小島よしおさんだ。
彼のやっているミニマルな暮らしは、頭と身体を鍛えるべくして用意した、最高の環境だった。ここを読むだけでもこの一書の価値はあるだろう。
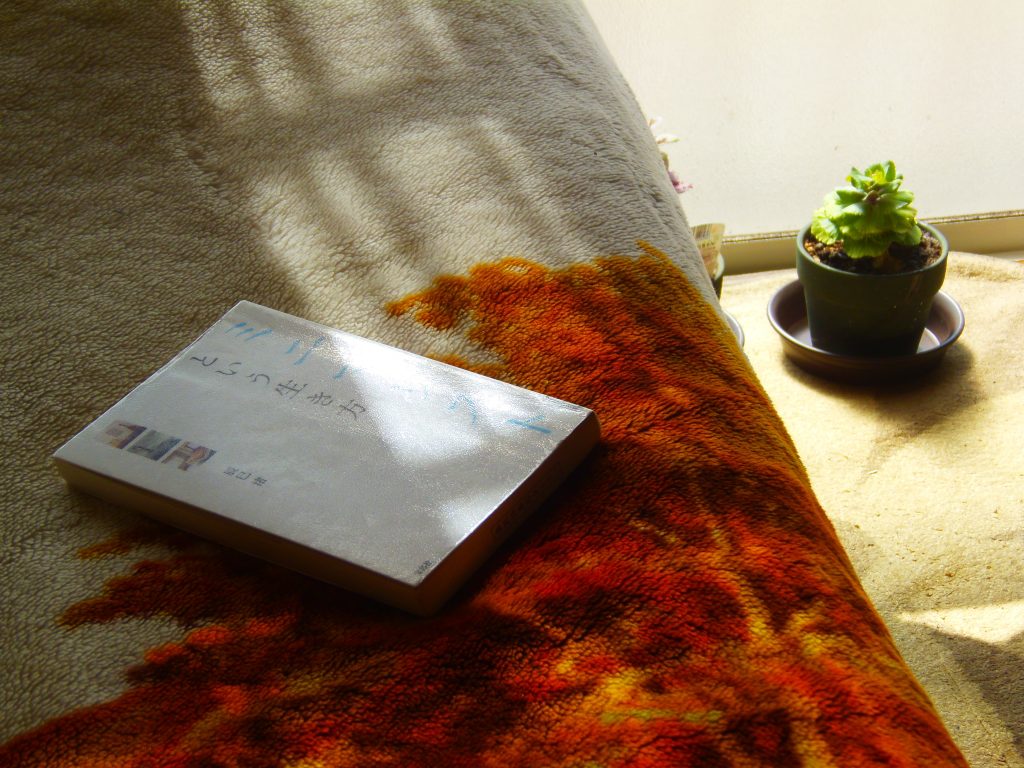
さ!3月。
ミニマリストに興味のある人も、反感のある人も、片づけや掃除に動きだそう。
たった一冊の本で人生が変わるかもだし、たった半日家の中を掃除しまくるのでもやや、人生に変革が生まれるかも(笑)
3月は春の期待と予感の月だから。