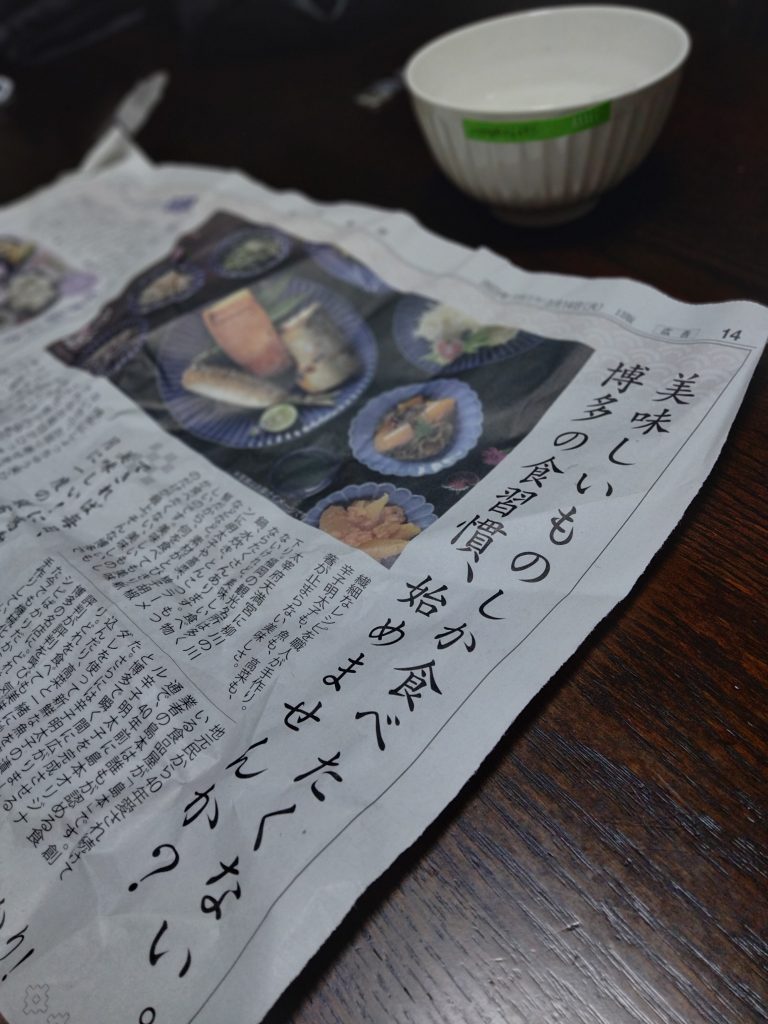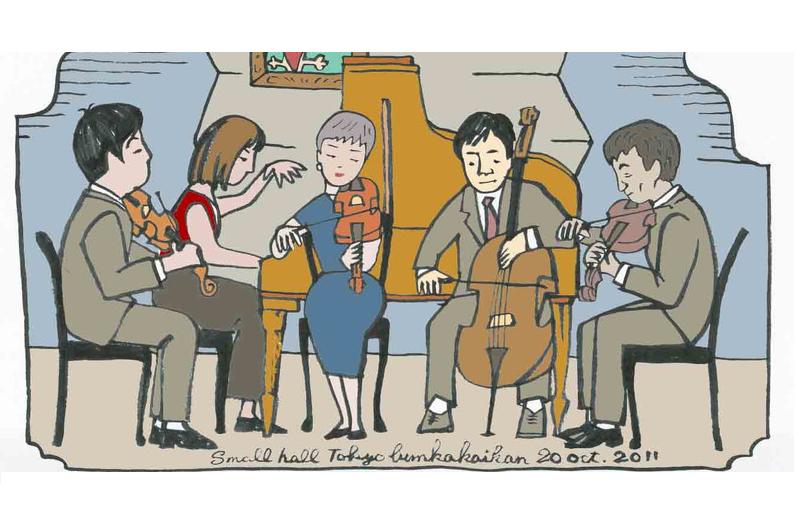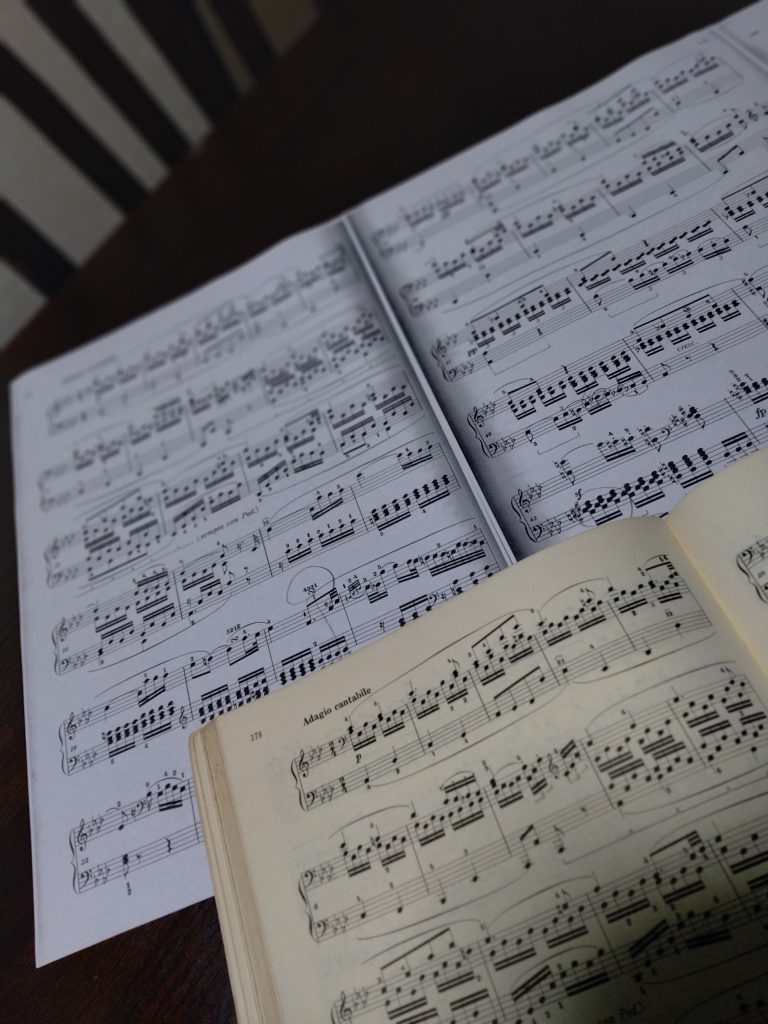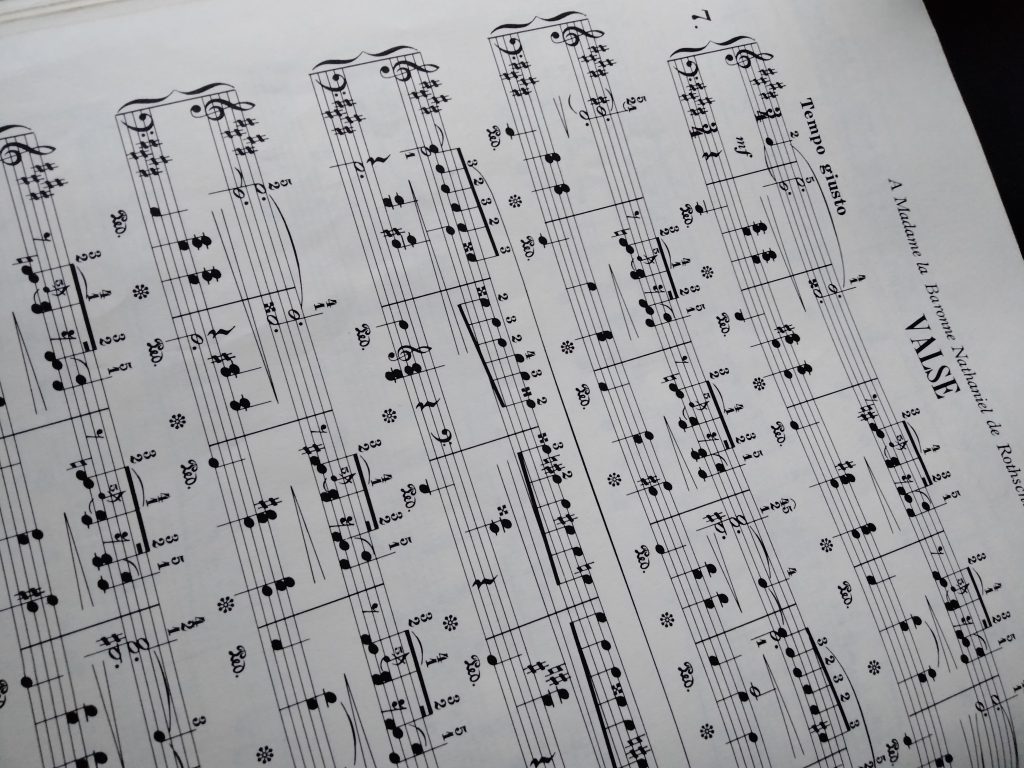【ブログ新規追加1122回】

昨日、TBS放映「がっちりマンデー!!」にメディアプラットフォームの旗手である「note」が特集された。関連資料はこちら→https://tver.jp/episodes/ep7kch2pkh(TVer;がっちりマンデー!!儲かるnote)
と、しょっぱなから、「儲かる!」を売りにした番組でいささか、「ええ~~?!そんなに儲かるの?」と、怪しい雰囲気プンプンだ。
ここで、noteについて改めて紹介しよう。
会員数は700万人(2023年8月時点)に達している。
noteとは、クリエイター(プロ・アマ問わず)が文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォーム。
noteはブログと同じく情報を発信できるサービスで、「コンテンツを有料販売できる」「文章を書くことに特化」など独自の特長がある。
「がっちりマンデー!!」でのnoteの紹介では、初心者でもなにかしらの文章を書ける人が簡単に記事をアップできて、しかも有料販売できるプラットフォームだと説明されていた。
また、noteの大きな特徴としては、他のブログサイトのような広告が記事内に存在しないことを挙げられて、記事を書くクリエイターのためにそうしているんだとも言われていた。
noteの特徴と使い方関連資料はこちら→https://note.com/info/n/nea1b96233fbf(noteの特徴、使い方、機能紹介)
で、TVで流れていた「儲かっているクリエイターさん」の現在の記事はnoteのTOPページにベストセラーとして載っているから、一度閲覧してもいいかも。
記事内容は、着回し術、野球の球速を上げる方法、つまみ細工、投資など。
一見するとごく普通の方々だが、皆さん有料記事投稿で100万円以上稼いでいらっしゃると!驚き。
しかし、儲かる記事をクリエイターだけで仕上げているわけではない。そこには、ちゃんとプロの編集者がついて、タイトルから内容までをがっちり仕上げている(独自開発の生成AIを利用している)から閲覧数もうなぎ上りなんだそうだ。
有料記事がバンバン売れて驚いている!とクリエイターさんがおっしゃっていた。
確かに驚くよね!プロの物書きでもない方の記事でしょ?
でも、「そこにしかないノウハウがあれば売れる」のだとnote社長加藤貞顕氏が言われていたのが印象的だった。
noteは誰でも手軽に情報発信できるサービスの究極かも。
いいことばかりじゃなくて、デメリットも簡単に記載する。
• デザインのカスタマイズ不可。•一部を除き広告掲載不可。• SEO対策が難しい。など。
★★★
さて、わたしも、noteは約4年前から取り入れている。ただ、記事を書いたことは一回もない。
「みんなのフォトギャラリー」という写真を使った投稿を専門にやってきた。簡単に説明しよう。
「みんなのフォトギャラリー」は、いわばnoteのクリエイターのためのフォトギャラリー機能である。
自分の画像を投稿したり、ほかのクリエイターが投稿した画像を自分の記事の見出し画像としてつかうことができる。
「みんなのフォトギャラリー」への画像提供は、noteアカウントがあればだれでも行うことができる。
提供した画像を、だれかが自分の記事の見出し画像として使用した場合は、その見出し画像の下に提供クリエイターの名前が表示される。
また、提供クリエイターに「○○さんがあなたの画像を使用しました」と通知が届く機能だ。(関連資料;https://www.help-note.com/hc/ja/articles/900003455886–)
この4年間で75枚の写真を投稿してきた。
投稿写真をクリエイターさんが自由に選んで使うわけだが、現在までで約350人以上の方々の作品に使われてきた。
そして、100人、200人、300人と、私の写真を利用される回数が増えるたびに「記念」として、有料ににした写真は現在4枚ほど。
まあ、がっちり儲けよう!とかまったく考えていないのね。
あくまで記念としてささやかに有料販売するだけで、小銭を稼いでいるという利用方法なのだ。
そうそう、今日もおひとりのクリエイターさんが利用くださった。さっそく記事を読んで一言コメントしてきた。
これを毎週続けているのだ。細く、楽しく、嬉しいつながりよ。
趣味の写真で、玄人はだしでもないし加工も一切なし。
それでも作品のTOPを飾るのに使ってもらえてとても嬉しい!
一番びっくりしたのは、某有名作家のクリエイターさんが使ってくださったことかしら。
ま、いい思い出として記憶の片隅においておこう。
コミュニティは敬遠していて、自分と少しのフォロワーさんとつながるnoteでの活動話を書いてみた。
それでは、また!