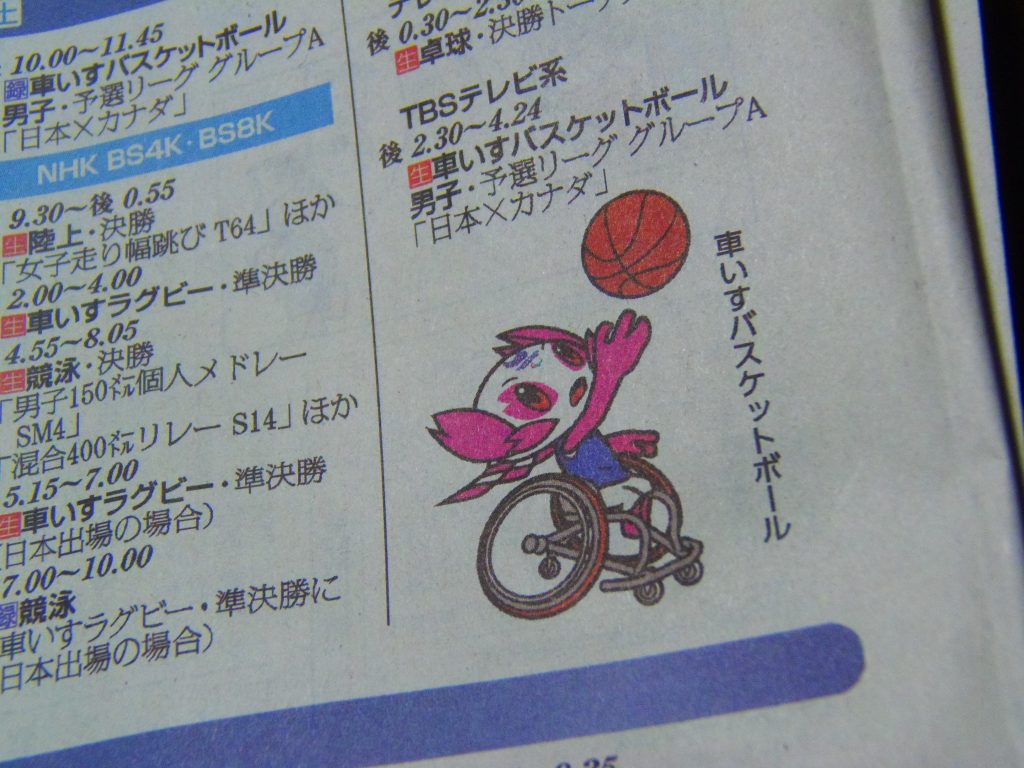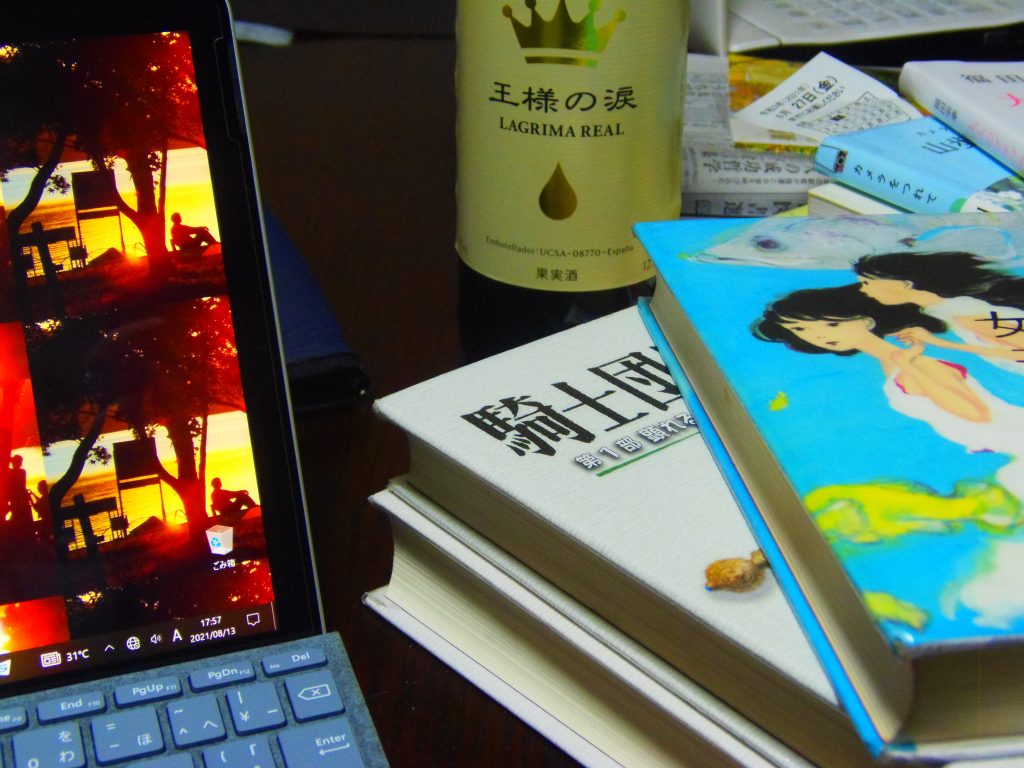【ブログ新規追加457回】

文章の上手い・下手は才能の加減によるものだろうか?
いいえ、読みやすく・わかりやすい文章を書くために必要な手順というか、テクニックとコツがあるのだ。
久しぶりに「文章」に関するテーマで1本書いてみようと思い立った。
今まで、試行錯誤しながら毎日ブログを書き綴ってきた。
以前参照した書籍や、お世話になった編集者から教えてもらったテクニックやコツを4つほど書き出してみよう。
この4つを押さえるだけで、一定の水準を保つ文章を書くのも可能だ。
ほんとよ(笑)
★
① 下調べをしよう
仕事の企画書や日報、客先へのメール、ブログ、SNSへの投稿など、他人に読ませる、読んでもらうのを前提とした文章を書く場合「全文参照」最後まで読んでもらえる文章を書かないわけには行かない。
わたしごとだが、仕事のメールや報告であれば何度でも読み返して書いてあることの真意を読み解くが、これが仕事じゃない場合どうだろう。
SNSとかでは、まずほぼ読まない。タイトルがない、思いつきのつぶやきはスルーする。
写真で何かを表現してくれている記事は比較的目を通すぐらい。ただ、同業(出版)のブロガーさんの記事はちゃんと開いて最後まで読むことが多い。それは、同業という関係もあるが、それ以上に記事に内容が豊富にあるからだ。
もちろん、すべて読んだとしてもあまり勉強にならない場合もあるが、最後まで読ませる価値があると思ったら全文参照する。
さて、最後まで読ませる文章をどうやって書くのか?
それは、書く内容(テーマ)の下調べ、事前準備を徹底的にやるのに他ならない。
なぜ、下調べが必要なのか?はこの書籍に網羅されているからぜひ、お手元に1冊持たれるといい。
『書く力』池上彰・著(朝日新書)
• 簡単レビュー
わかりやすい言葉を選び、TVや書籍で多くの「人」をあっという間にテーマに引き込む技が素晴らしい池上彰氏。その池上氏と読売新聞1面のコラム「編集手帳」を15年間書き続けてきた、名文家の竹内政明論説委員の文章書き対談だ。
誰でも読める・読みやすい・うなる文章の書き方のエッセンスを伝授する。(レビューはここまで)
今まで、2度、池上彰氏の世界の政治セミナーを受けてきた。その時、印象的だったのが、「すべてアナログが大事」なんだと、言われていた。このネット時代にアナログ?って?
池上氏は今でこそ、ネットでも情報を読むようになったが、基本は紙新聞を毎朝12紙ざざ~っと読み出すのが仕事のスタートだと言われていた。
ヤフー12文字のネット記事の信憑性も新聞を読んで推し量ってきたそうだ(※ この話も3年前だから現在はどうなのかしら?)
と、多角的に世界の情勢を読みとくには新聞と書籍が手放せないと話されていた。
こうして、アナログに徹した事前の情報収集から、的を得た文章や言葉を引き出しているのだ。
長くなったが、①は書く内容の事前準備はきっちりとしよう!ってことだ。
追加をひとつ。
伝える力【話す・書く】研究所所長・山口拓朗氏(PRESIDENT誌では著名)が言われていたのが、「情報収集にあっては『これで文章を書こう』という意識を常に持っておくと、アンテナが立ち欲しいと思っていた情報が次々と自然に入ってくるものだ。そうなると行動も変わってくる」と。
例えば、工場視察レポートを書く場合、視察前に「課題」になりそうなことがらを想定しておく。(例えば、コスト、人事面、SDGsなど)
実際に視察した時に注意して見るポイントを絞っておけば、小さくとも「気づき」は得られる。
要するに「何を書かなければならないのか?」を明確にしたうえで情報を集めるのがよいと言われている。
書く部品さえ揃えば上手い文章でなくてもいい。丁寧に見た・聞いたことを書いてみようと伝えられていた。
大事な観点だ。
「自分の記憶やひらめきを過信しない」これが大切なのだ。
② 文章をまとめるために使う飛び道具(接続詞)はこれ!
小説の独創性のある文章以外は、基本的に「読みやすく・わかりやすい」これが一番大事だ。
一定の人にしか通じないスラングを誰でも読めるSNS上に書くのもNGだと感じる。
必要なのは「正しい情報をわかりやすく書く」これだけだ。
あれも、これもと詰め込んだモリモリの文章は、読む側に想像以上のストレスを与える。
読みにくさ、わかりにくさの最たる原因は、「文章の組み立て=構成」だろう。
そこで、文章の組み立てに必要な「接続詞」という飛び道具を使おう!という提案だ。
わたしが良く使っているのが「さらに」「もちろん」「しかし」「しかも」「というわけで」などの飛び道具を使って、文章をつないでいるのだ。
この接続詞があるおかげで、内容や意味が「深くつながる」だけでなく、より「理論的に展開できる」有難い飛び道具なのだ(笑)
③ 書き終わったら必ず読み返そう
一生懸命書き上げた文章も、すぐにアップロードせず、何度か読み返してみよう。
自分の文章であっても、他人の文章を推敲する視点が必要だ。
慣れてくれば、推敲なしのアップは怖くてできなくなるよね。
でも、わたしはやっちゃう時がある(泣)
だから、戒めるために③としたの。
スッキリとした文章にしてからアップしよう。
④ テンポのよい文章になっているかどうか?点検しよう
リズムのよい文章こそ全体の流れを何度も確認し、バランスも良く図られているものだ。
これを実現するには、書いた文章を「音読」するのが一番いい方法だ。
わたしごとだが、これまで同じ出版社から2冊の書籍を出させて頂いた。電子書籍だから紙書籍より推敲やら編集者のダメ出しが圧倒的に少ない。
しかし、編集者が求めてきたのは、「全文を5回音読」して、流れの悪い部分を事前に手直ししてから稿了してほしいと言われた。
わたしは、言語障害があるので大きな声で読むのができず相談したら、「つぶやいて下さい」と。
「それで流れはつかめます!」と、教えて頂いた。
編集者とわたしとそれぞれが5回「音読」をし、流れの悪かった部分をチェックし、お互いの照らし合わせをしたらほぼ同じ箇所だった(驚き!)
それからは、どんな文章でも書いたら「音読」するクセがついたのだ。
これは、文章上達の「秘訣」であり「コツ」だね。
 写真は「うかい鳥山」
写真は「うかい鳥山」
というわけで、久しぶりに「文章まとめ術」を書いてみた。
① 下調べする
② 接続詞を使う
③ 読み返す
④ 全文音読
この4つをちゃんとやって行くと、自分の文章のクセもわかるし、自分の文体の把握もできるはず。
夏休みの自由研究が終わったみたいな爽快感だわ!
さて、アイスたべよっと(笑)