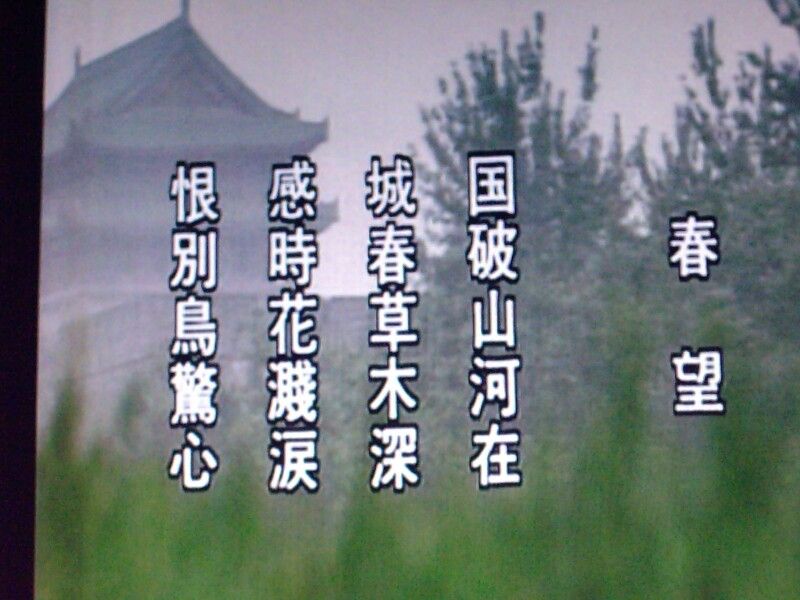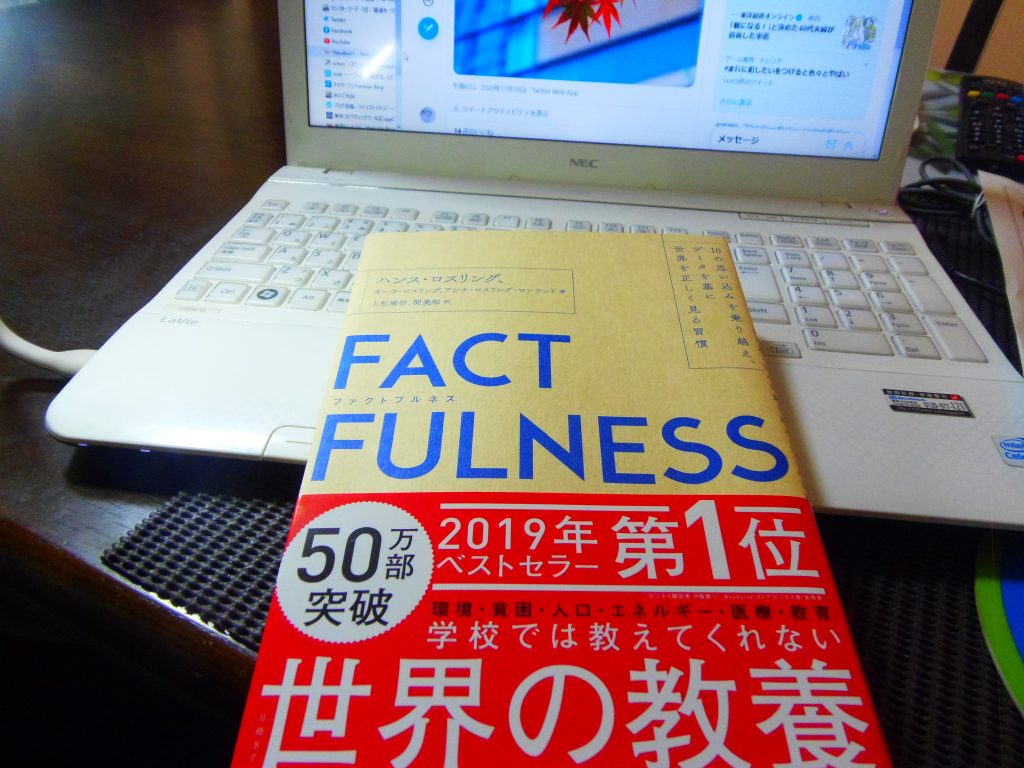【ブログ新規追加195回】
● なぜ、年末の片づけは早めがいいのか?

年末早めの片づけは何がそんなにいいのか?
それは、片づけや掃除って思いのほか時間がかかるもの。年末は不用品の処分にも、焼却場が長蛇の列になってしまうことや、日常のゴミ収集も大量に出されていつもより出しづらい。
ゆえに、世間の常識的習慣をちょっとずらすのがいいのだ。
師走の声を聞くすこし前から、計画的に片づけてしまうほうが、より年末の時間をゆったりと楽しめる。わたしは、一年を振り返る年末の時間をことのほか大切にしている。
さて、タイトルのノスタルジーの話をまとめてみた。
● ノスタルジーとは
ノスタルジーとは・・・「時間や時代を懐かしむ気持ち」を意味する仏語。
ノスタルジーは「過ぎ去った時間・時代を懐かしむ気持ち」「故郷を懐かしく思う気持ち」という意味である。
フランス語の「nostalgie」がカタカナ語として定着した。(引用先リンク→https://biz.trans-suite.jp/34598)
わたしが思うノスタルジーは、家の片づけに尽きる。
5年前に亡くなった母の遺品の整理に、思いがけず時間がかかってしまった。
それは、昔を懐かしむ気持ちが「自然と片づけという作業を遅らせていた」のだと感じている。
亡くなった当時の様子をちょっとエッセイにしてみた。
★
「片づけはノスタルジーとの決別」

葬儀を終えた翌日から、3日ほどかかって母の家の片付けを私達夫婦と弟夫婦でやった。
遺品といっても、母の残した物はタンスなど大物以外比較的新しいものが多く、介護期間も短かったので一般的な介護用品や昔の持ち物などはほとんどない。
なんだけれども、家族のアルバムや賞状、記念の品などノスタルジーたっぷりの物達の多さに、皆ふ〜っとため息が出た。
後から後から出てくる物の多さは本当に恐ろしくなるほどの状況。
やっと押入れの1つが片付いたとおもったらその上の天袋から出てくる懐かしのアルバムや引き出物の山々・・・もう恐怖映画を見ているような気分(笑)
でも、久しぶりに昔の写真を見ながら大笑いしたりで、それはそれで懐かしくもあり弟との大切な思い出ともなった。
しかし、そんなノスタルジーの蜜月は2日で終了。
弟「ねえちゃん、もうよそう・・・」と言われて、ハッと!我に返った。
山のような片付けも、最後に家具などの大物を引取業者にまかせ、「一人の人生の片付け」という大仕事が終わった。
★
人生をいくら、振り返っても、生きている以上前へ、前へと、進まなければならない。片づけはしんみりした気持ちや己の執着を断ち切る、大切な戦いなのだ。

母の残したアルバムをどうしようか?と考えた時、とっさに「断・舎・離」の定義を思い出した。
「断舎離とは、必要ないけれど捨てるのは後ろめたいという、執着の心を断って物を捨てる技術」というインド思想。
要するに「思い切る」ために行う作業。
そうだ、もうこれから使わないただ取っておくためだけのものは、身内で見て思い出に昇華したので一部の形見を除き思い切りよく捨てることにした。
無駄なコストを省くことは大いなるエコである。
エコ社会への貢献を考えると「断・舎・離」の思想は物を増やし過ぎる社会への批判とも取れる。
ただの経済効果優先主義でなく、ノスタルジーとの決別とも取れよう。
しかしノスタルジーを求め、古いものやそういった物にお金を出す人も最近は多い。
ただ使わないものや古くて忘れられた物を安易に廃棄処分する事には、いつかは社会的にも批判の反動が起こってきそうな予感がする。
ちょっと大げさだけれど「ミニマリスト」の行く末はどうなるんだろう?なんて余計なお世話を考えてしまう。
物を捨てて確保した空間が一番贅沢だと、ミニマリストの間では盛んに言われている。
実際私も、ものすごい捨て魔の自称シンプリニストだ。
そんな自分でも思い入れのある物たちへの扱いには慎重にならざるをえないところがある。
「断・舎・離」提唱者のやましたひでこ氏にも、きっと思想化された「片付け」に対する批判が相当あったように感じる。
それをご自身のパワーに変えて講演や執筆をされてきたのではないか?と思うのである。
現代の過剰評価社会の中で頑張っているんだなあ、と感慨深く思った。「否定もパワーに変える」と。恐るべし。
年末にはすっきりと身の回りを片付けて、「変わりたい」じゃなくて、「変われる」人になる!と意気込んでいる(笑)