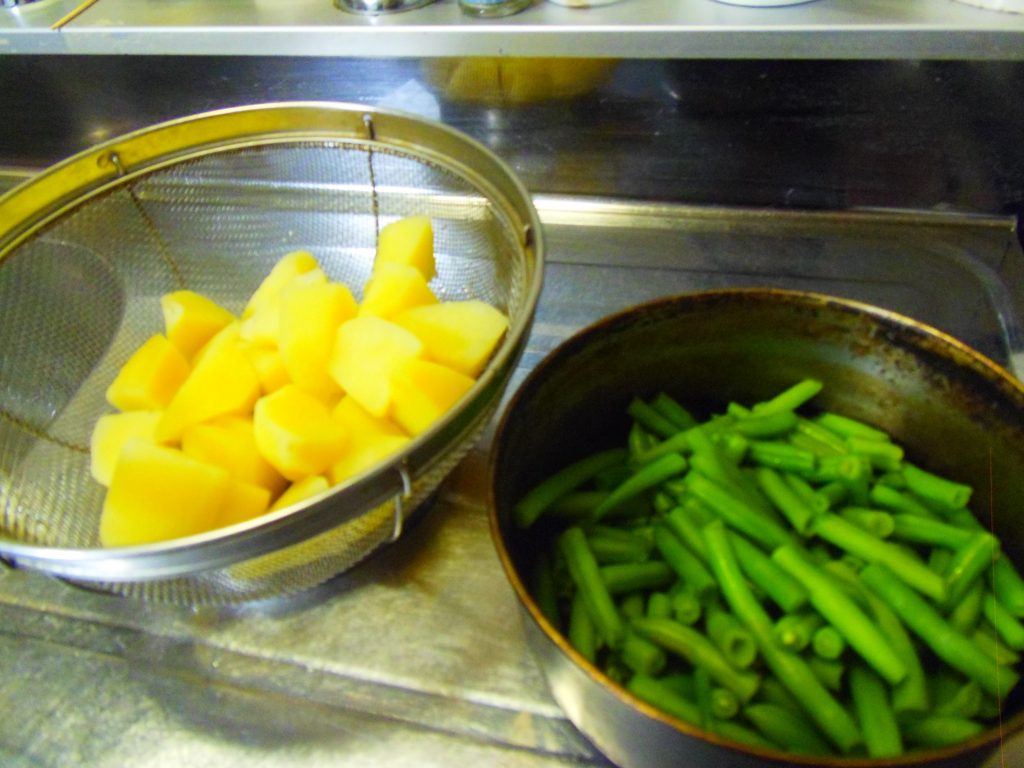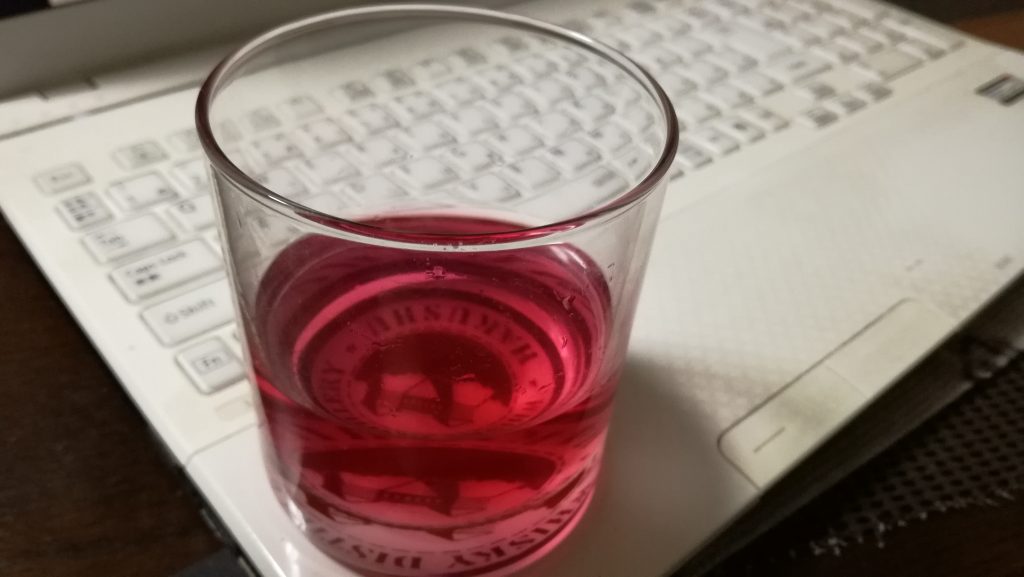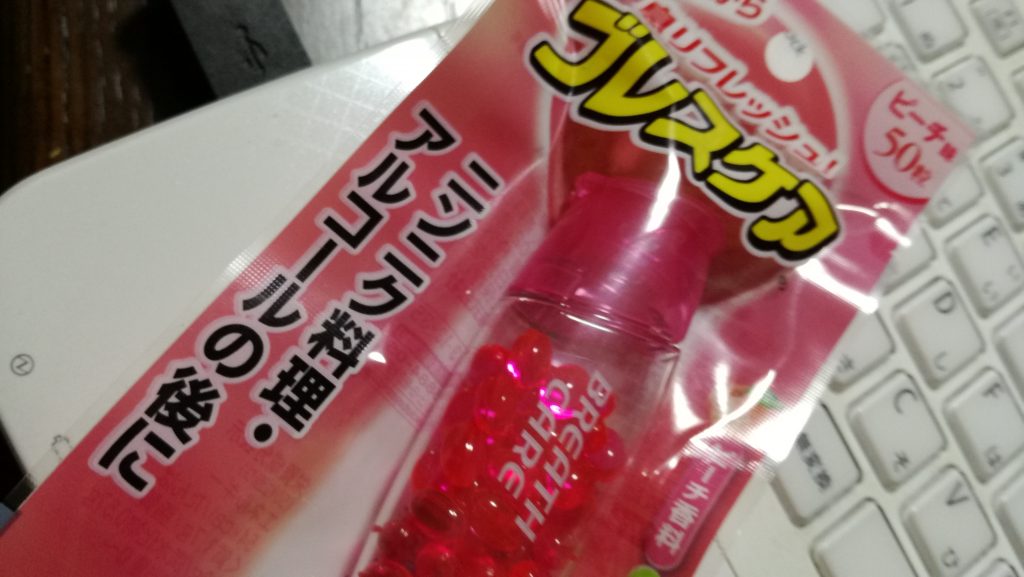【ブログ更新89回】
真夏になったから、改めて水の話をしよう。早速だが、頭痛、慢性疲労、自律神経失調症、めまい、不眠、冷え、動悸など、ほぼ更年期障害に関係する身体の不調は水で治せる。
● 水の飲み方や身体の不調に合わせた水の選び方の本があった!
水を上手に取ることで、身体の4つの不良体液を流すという治療を続ける森下克也医師の書籍を紹介する。
この本では、どんな水でもいいわけではなく、症状によって、水を飲み分ける考え方が書かれていることと、スクワットなどの体操を取り入れた不調改善法が学べる素晴らしい一冊。ぜひ、お手元にどうぞ。
医師が教える 不調を治す水の飲み方・選び方 「4つの体内水」を流して健康になる本 森下克也・著

● 大病で入院中に飲んだ水は一日コップ12杯!
この夏もどれだけの水を飲んだであろうか。
わたしは、脳出血で12年前、真夏の8月に緊急搬送された経験がある。瀕死の時、辛く感じたことは、おそらく発病の発端は、疲れと暑さからの脱水症状と熱中症じゃないか?と。
何とか命を取り留めて、ICUから一般病棟に移ってからは水分補給の特訓が始まった。食事はすべて流動食、そして水は一日コップ12杯!必ず飲み干さなければいけない。
スープや味噌汁とは別にこれだけの水を飲むのは精神的にもしんどく、追い込まれそうだった。固形物を食べないと水はそんなに飲めないものだ。
身体の麻痺が重く、自力でトイレに行けない。だから、どうしてもガバガバ水を飲むことにためらいがあった。しかし、飲まないことには、体の中に停滞している悪い体液を流すことができにくいのだそうだ。
真水だけでなく、12杯の半分はハトムギ茶にして味を変えることで、この水攻めとも言える治療に挑むことができた。
発病12年経った今でも、この習慣は続けていて、朝一番に飲むのは常温の真水コップ1杯。お茶や食事の汁物なども軽く計算に入れて、何とか一日2ℓを目安にこなしている。
しかし、一日2ℓの弊害もささやかれているのも事実だ。あくまでも、何のためか?という観点から、個人にあった水分摂取を心がけていきたいものだ。
それでも、夏場はいやがおうでも色んな飲み物を口にする機会が多いので、量的にはクリアしやすいと思う。
昨今、炭酸水をはじめ、さまざまな種類のミネラルウォーターが熱中症対策も手伝って人気を集めているとか。くだものなどのフレーバーが入ったウォーターも種類が豊富。味を変える楽しみも利用して脱・脱水だわね。

● 体と水の関係
体と水の関係だが、人間の体の60~70%は水分でできているとよく耳にする。実は、体に占める水分の割合は一定ではなく、年齢や体型、性別などによって異なる。
従って「女性・高齢者・乳幼児」はよりこまめな水分補給が大切だ。では1日にどれくらいの水を飲めば良いか。
一般的には(運動などで汗をかかない場合)、食事で800〜1000ml、飲料から1200〜1500ml補給できれば良い。
汗をかく時期は脱水症状予防のため少し多めで1500〜2000mlを心がけると良いということだ。
けっこうな水分量だ。一度、自分が1日にどれくらい水分を摂っているか軽く計算してみると良い。
● 水を飲むタイミングだが、心がける点が3つある
①朝一番(奇跡の水、命の水と呼ばれる。)
②発汗の前後(喉が乾く前、入浴前、就寝前など)
③食事のとき(食事をとりながらが効果的)

7月7日、ホットなニュースとして登場した、無印良品給水機。マイボトル持参で、無料で水が頂ける・神技情報はこちら→https://ameblo.jp/lea1987/entry-12609623826.html
美しく、健康な人ほど、水を正しく飲んでいるんではないだろうか。
「家ハ雨のもらぬほど、食事ハ飢えぬほどにて足る事也、
是れ仏の教、茶の湯の本意也」
千利休 「南方録」より